公共政策をめぐる戦い
【公共政策では、市場や国家や市民社会の役割のような、重要で基礎的な思想をめぐって論争される。なぜなら、この大きな枠組みが個別の認識と、特別な利害関係を考慮した現実的政策に影響を与えるからである。(ジョセフ・E・スティグリッツ(1943-))】公共政策をめぐる戦い
(1)利害関係
実際には、特別な利害関係を考慮した現実的政策が争われている。
(2)表向きの主張
表向きの主張では、効率性や公平さに焦点があてられる。すなわち、あくまでも自分たちの利益ではなく、他の人々の利益にもなるという主張がなされる。
(3)枠組み思考の重要性
市場や国家や市民社会の役割のような、重要で基礎的な思想が、大きな“枠組み作り”を行い、個別の認識は、この枠組みの影響を受ける。
「不平等の政治学
ここまで、どのようにしてわたしたちの認識が“枠組み作り”の影響を受けるか説明した。
だから、今日の戦いの多くが不平等の枠組み作りの戦いであることは驚くにあたらない。
美と同じく公平さも、少なくとも多少は見る人の見かたに左右されるし、最上層の人々は、いまのアメリカにおける不平等が公平なものに見えるような、少なくとも許容範囲内のものに見えるような枠組みになっていることを確信したいと思っている。
不公平だと認識されると、職場の生産性に響くおそれがあるだけでなく、不平等を緩和しようとする法律が制定されることにもなりかねないからだ。
公共政策をめぐる戦いにおいては、特別な利害関係を考慮した現実的政策がどのようなものであろうとも、一般大衆の会話では、効率性や公平さに焦点があてられる。
わたしが政府の役職に就いていたころ、産業への助成金を求める嘆願者が、財源が豊かになるからという理由だけで助成金を求めるのを耳にしたことは一度もない。むしろ、嘆願者は公平という言葉を使って――そして、そうすることがほかの人々の利益にもなるという表現を使って――自分たちの要望を伝えてきた。
同じことは、アメリカで不平等を拡大させた政策についても言える。
“枠組み作り”についての戦いは、まず、わたしたちが不平等をどう見るのか――不平等はどのくらい大きいのか、その原因は何か、どのように正当化できるのか――が焦点となる。
それゆえ企業のCEO、特に金融部門のCEOは、自分たちの高給は社会に大きな貢献をした成果だから正当化できると主張してきた。このような貢献を続ける意欲を持つには高給が必要だということを、他人に(そして自分自身に)納得させようとしてきた。だからこそCEOの高給は報奨金と呼ばれているのだ。
しかし、金融危機が、そういうCEOの主張はごまかしだということを白日のもとにさらした。4章で触れたように、報奨金という名称の報酬は、とても報奨金と呼べる代物ではなかった。業績がよければ報酬は高くなったが、業績が悪くても報酬は高いままだった。変わったのは名称だけだ。業績が悪いと、報酬の名称は“慰留金”に変えられた。」
(ジョセフ・E・スティグリッツ(1943-),『不平等の代価』(日本語書籍名『世界の99%を貧困にする経済』),第6章 大衆の認識はどのように操作されるか,pp.231-232,徳間書店(2012),楡井浩一,峯村利哉(訳))
(索引:公共政策をめぐる戦い)
 |
(出典:wikipedia)
 「改革のターゲットは経済ルール
「改革のターゲットは経済ルール21世紀のアメリカ経済は、低い賃金と高いレントを特徴として発展してきた。しかし、現在の経済に組み込まれたルールと力学は、常にあきらかなわけではない。所得の伸び悩みと不平等の拡大を氷山と考えてみよう。
◎海面上に見える氷山の頂点は、人々が日々経験している不平等だ。少ない給料、不充分な利益、不安な未来。
◎海面のすぐ下にあるのは、こういう人々の経験をつくり出す原動力だ。目には見えにくいが、きわめて重要だ。経済を構築し、不平等をつくる法と政策。そこには、不充分な税収しか得られず、長期投資を妨げ、投機と短期的な利益に報いる税制や、企業に説明責任をもたせるための規制や規則施行の手ぬるさや、子どもと労働者を支える法や政策の崩壊などがふくまれる。
◎氷山の基部は、現代のあらゆる経済の根底にある世界規模の大きな力だ。たとえばナノテクノロジーやグローバル化、人口動態など。これらは侮れない力だが、たとえ最大級の世界的な動向で、あきらかに経済を形づくっているものであっても、よりよい結果へ向けてつくり替えることはできる。」(中略)「多くの場合、政策立案者や運動家や世論は、氷山の目に見える頂点に対する介入ばかりに注目する。アメリカの政治システムでは、最も脆弱な層に所得を再分配し、最も強大な層の影響力を抑えようという立派な提案は、勤労所得控除の制限や経営幹部の給与の透明化などの控えめな政策に縮小されてしまう。
さらに政策立案者のなかには、氷山の基部にある力があまりにも圧倒的で制御できないため、あらゆる介入に価値はないと断言する者もいる。グローバル化と人種的偏見、気候変動とテクノロジーは、政策では対処できない外生的な力だというわけだ。」(中略)「こうした敗北主義的な考えが出した結論では、アメリカ経済の基部にある力と闘うことはできない。
わたしたちの意見はちがう。もし法律やルールや世界的な力に正面から立ち向かわないのなら、できることはほとんどない。本書の前提は、氷山の中央――世界的な力がどのように現われるかを決める中間的な構造――をつくり直せるということだ。
つまり、労働法やコーポレートガバナンス、金融規制、貿易協定、体系化された差別、金融政策、課税などの専門知識の王国と闘うことで、わたしたちは経済の安定性と機会を最大限に増すことができる。」
氷山の頂点
日常的な不平等の経験
┌─────────────┐
│⇒生活していくだけの給料が│
│ 得られない仕事 │
│⇒生活費の増大 │
│⇒深まる不安 │
└─────────────┘
経済を構築するルール
┌─────────────────┐
│⇒金融規制とコーポレートガバナンス│
│⇒税制 │
│⇒国際貿易および金融協定 │
│⇒マクロ経済政策 │
│⇒労働法と労働市場へのアクセス │
│⇒体系的な差別 │
└─────────────────┘
世界規模の大きな力
┌───────────────────┐
│⇒テクノロジー │
│⇒グローバル化 │
└───────────────────┘
(ジョセフ・E・スティグリッツ(1943-),『アメリカ経済のルールを書き換える』(日本語書籍名『これから始まる「新しい世界経済」の教科書』),序章 不平等な経済システムをくつがえす,pp.46-49,徳間書店(2016),桐谷知未(訳))
(索引:)
ジョセフ・E・スティグリッツ(1943-)
スティグリッツの関連書籍(amazon)
検索(スティグリッツ)


 「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。
「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。
 「私たちヒトは、多くの種類の苦しみ[受苦]に見舞われやすい[傷つきやすい]存在であり、私たちのほとんどがときに深刻な病に苦しんでいる。私たちがそうした苦しみにいかに対処しうるかに関して、それは私たち次第であるといえる部分はほんのわずかにすぎない。私たちがからだの病気やけが、栄養不良、精神の欠陥や変調、人間関係における攻撃やネグレクトなどに直面するとき、〔そうした受苦にもかかわらず〕私たちが生き続け、いわんや開花しうるのは、ほとんどの場合、他者たちのおかげである。そのような保護と支援を受けるために特定の他者たちに依存しなければならないことがもっとも明らかな時期は、幼年時代の初期と老年期である。しかし、これら人生の最初の段階と最後の段階の間にも、その長短はあれ、けがや病気やその他の障碍に見舞われる時期をもつのが私たちの生の特徴であり、私たちの中には、一生の間、障碍を負い続ける者もいる。」(中略)「道徳哲学の書物の中に、病気やけがの人々やそれ以外のしかたで能力を阻害されている〔障碍を負っている〕人々が登場することも《あるにはある》のだが、そういう場合のほとんどつねとして、彼らは、もっぱら道徳的行為者たちの善意の対象たりうる者として登場する。そして、そうした道徳的行為者たち自身はといえば、生まれてこのかたずっと理性的で、健康で、どんなトラブルにも見舞われたことがない存在であるかのごとく描かれている。それゆえ、私たちは障碍について考える場合、「障碍者〔能力を阻害されている人々〕」のことを「私たち」ではなく「彼ら」とみなすように促されるのであり、かつて自分たちがそうであったところの、そして、いまもそうであるかもしれず、おそらく将来そうなるであろうところの私たち自身ではなく、私たちとは区別されるところの、特別なクラスに属する人々とみなすよう促されるのである。」
「私たちヒトは、多くの種類の苦しみ[受苦]に見舞われやすい[傷つきやすい]存在であり、私たちのほとんどがときに深刻な病に苦しんでいる。私たちがそうした苦しみにいかに対処しうるかに関して、それは私たち次第であるといえる部分はほんのわずかにすぎない。私たちがからだの病気やけが、栄養不良、精神の欠陥や変調、人間関係における攻撃やネグレクトなどに直面するとき、〔そうした受苦にもかかわらず〕私たちが生き続け、いわんや開花しうるのは、ほとんどの場合、他者たちのおかげである。そのような保護と支援を受けるために特定の他者たちに依存しなければならないことがもっとも明らかな時期は、幼年時代の初期と老年期である。しかし、これら人生の最初の段階と最後の段階の間にも、その長短はあれ、けがや病気やその他の障碍に見舞われる時期をもつのが私たちの生の特徴であり、私たちの中には、一生の間、障碍を負い続ける者もいる。」(中略)「道徳哲学の書物の中に、病気やけがの人々やそれ以外のしかたで能力を阻害されている〔障碍を負っている〕人々が登場することも《あるにはある》のだが、そういう場合のほとんどつねとして、彼らは、もっぱら道徳的行為者たちの善意の対象たりうる者として登場する。そして、そうした道徳的行為者たち自身はといえば、生まれてこのかたずっと理性的で、健康で、どんなトラブルにも見舞われたことがない存在であるかのごとく描かれている。それゆえ、私たちは障碍について考える場合、「障碍者〔能力を阻害されている人々〕」のことを「私たち」ではなく「彼ら」とみなすように促されるのであり、かつて自分たちがそうであったところの、そして、いまもそうであるかもしれず、おそらく将来そうなるであろうところの私たち自身ではなく、私たちとは区別されるところの、特別なクラスに属する人々とみなすよう促されるのである。」
 「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
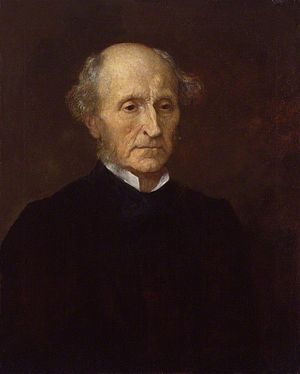 「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」




