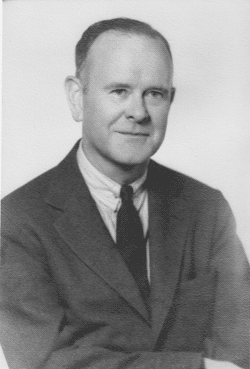半影的問題における決定の本質
【半影的問題における決定の本質の理解には次の点が重要である。(a)法の不完全性、(b)法の中核の存在、(c)不確実性と認識の不完全性、(d)選択肢の非一意性、(e)決定は強制されず、一つの選択である。(ハーバート・ハート(1907-1992))】(1.2)追記、(4)追記。
(1.2)この批判の基準は、道徳的なものとは限らない。
(1.2.1)このケースでの「べき」は、道徳とはまったく関係のないものである。
(1.2.2)仮に、ゲームのルールの解釈や、非常に不道徳的な抑圧の法律の解釈においても、ルールや在る法の自然で合理的な精密化が考えられる。
(4)問題解決のために、重要だと思われること。
(1)(2)(3)の要請を、すべて充たすことができるだろうか。この問題の解決のためには、以下の諸事実を考慮することが重要である。
(4.1)法は、どうしようもなく、不完全なものだということ。
(4.2)法は、ある最も重要な意味において、確定した意味という中核部分を持つということ。不完全で曖昧であるにしても、まず線がなければならない。
(4.3)私たちは、不確実性の中に生きており、不完全な法の下での決定の際、在る法の自然で合理的な精密化の結果として、唯一の正しい決定の認識へと導かれ得るのだろうか。それは、むしろ例外的であり、多くの選択肢が同じ魅力を持って競い合っているのではないだろうか。
(4.4)すなわち、存在している法は、私たちの選択に制限を加えるだけで、選択それ自体を強制するものではないのではないか。
(4.5)従って、私たちは、不確実な可能性の中から選択しなければならないのではないか。
半影的問題における合理的決定の解明には、(a)何らかの「べき」観点の必要性、(b)にもかかわらず、在る法と在るべき法の区別、(c)法の不完全性と中核部分の正しい理解、が必要である。(ハーバート・ハート(1907-1992))
(1)何らかの「べき」観点の必要性
半影的問題における司法的決定が合理的であるためには、何らかの観点による「在るべきもの」が、ある適切に広い意味での「法」の一部分として考えられるかもしれない。
(1.1)「べき」という言葉は、ある批判の基準の存在を反映している。この基準は、何だろうか。
(1.2)この批判の基準は、道徳的なものとは限らない。
(1.3)目標、社会的な政策や目的が含まれるかもしれない。
(1.4)しかし、在るものと、さまざまな観点からの在るべきものとの間に、区別がなければならない。
(2)在る法と在るべき法との功利主義的な区別は、必要である。
参照: 在るべき法についての基準が何であれ、在る法と在るべき法の区別を曖昧にすることは誤りである。(ジョン・オースティン(1790-1859))
参照: 在る法と在るべき法の区別は「しっかりと遵守し、自由に不同意を表明する」という処方の要である。(a)法秩序の権威の正しい理解か、悪法を無視するアナーキストか、(b)在る法の批判的分析か、批判を許さない反動家か。(ジェレミ・ベンサム(1748-1832))
(3)半影的問題の決定も、在る法の自然な精密化、明確化であると思える場合がある。
ルールの適用のはっきりしているケースと、半影的決定との間には本質的な連続性が存在する。すなわち、裁判官は、見付けられるべくそこに存在しており、正しく理解しさえすればその中に「隠れている」のがわかるルールを「引き出している」。
難解な事案における裁判官の決定を、在る法を超えた法創造、司法立法とみなすことは、「在るべき法」についての誤解を招く。この決定は、在る法自体が持つ持続的同一的な目的の自然な精密化、明確化ともみなせる。(ロン・ロヴィウス・フラー(1902-1978))
(3.1)難解な事案、すなわち半影的問題において、次のような事実がある。
(3.1.1)ルールの下に新しいケースを包摂する行為は、そのルールの自然な精密化として、すなわち、ある意味ではルール自体に帰するのが自然であるような「目的」を満たすものである。それは、それまではっきりとは感知されていなかった持続的同一的な目的を補完し明確化するようなものである。
(3.1.2)このような場合について、在るルールと在るべきルールを区別し、裁判官の決定を、在るルールを超えた意識的な選択や「命令」「法創造」「司法立法」とみなすことは、少なくとも「べき」の持つある意味においては、誤解を招くであろう。
(3.2)日常言語においても、次のような事実がある。
(3.2.1)私たちは普通、人びとが何をしようとしているかばかりではなく、人びとが何を言うのかということについても、人間に共通の目的を仮定的に考慮して、解釈している。
(3.2.2)例としてしばしば、聞き手の解釈を聞いて、話し手が「そうだ、それが私の言いたかったことだ。」というようなケースがある。
(3.2.3)議論や相談によって、より明確に認識された内容も、そこで勝手に決めたのだと表現するならば、この体験を歪めることになろう。これを誠実に記述しようとするならば、何を「本当に」望んでいるのか、「真の目的」を理解し、明瞭化するに至ったと記述するべきであろう。
(4)問題解決のために、重要だと思われること。
(1)(2)(3)の要請を、すべて充たすことができるだろうか。この問題の解決のためには、以下の2つのことが重要だと思われる。
(4.1)法は、どうしようもなく、不完全なものだということ。
(4.2)法は、ある最も重要な意味において、確定した意味という中核部分を持つということ。不完全で曖昧であるにしても、まず線がなければならない。
「そのルールは新しいケースを包含すべきだと私たちは考え、熟考した後、たしかに包含していると理解するに至る。
しかし、存在と当為の融合の例として思いあたるふしのある経験をこのように提示することが認められるとしても、次の二つのことに注意が向けられなければならない。
第一に、このケースでの「べき」は、Ⅲですでに説明した理由からして、道徳とはまったく関係のないものだということである。
新しいケースがルールの目的を補完して明瞭化するというのとまったく同じ意味が、ゲームのルールを解釈する際にも、また、非常に不道徳的な抑圧の法律であり、その不道徳性はそれを解釈することを求められている人も正しく理解しているような法律を解釈する際にもみられるであろう。
ゲームをしている人もまた、自分たちのしているゲームの「精神」が予想されていなかったケースにおいて何を要求するのかを考えることができる。
さらに重要なのは、このような議論を正当化すると思われる現象が法の領域においてどれほど稀な現象であるかということ、すなわち、あるルールの自然で合理的な精密化の結果、唯一の判決の仕方が私たちに強制されているという感覚がどれほど例外的なものであるかということを、検討の総括として心に銘記しておく必要がある。
解釈がなされるほとんどのケースにおいて、選択肢の中での選択、「司法立法」、さらには「命令」(恣意的な命令ではないけれども)といった表現の方が、現実の状況をうまく伝えるのは紛れもない事実である。
私たちが意識的な選択をしていることを自覚せず、認識されるのを待っているものを認識するという意識でいるならば、比較的確定した法の枠組の中でも、あまりに多くの選択肢があまりに同じく平等の魅力を持って競い合っているので、裁判官や法律家は、不確実なままに、自分自身の、また他人の行為の原則や意図や望みを解釈しようとする際に体験する経験に適切な表現を与える道を探らなければならない。
法の解釈を記述するのに、在る法と在るべき法との融合、分離不可能性という上述の表現を使用することは(裁判官は法を発見するのであって、決して法をつくるのではないという前の時代の物語のように)、私たちが不確実性の中に生きており、私たちは不確実な可能性の中から選択しなければならないという事実、また、存在している法は私たちの選択に制限を加えるだけで選択それ自体を強制するものではないという事実を覆い隠してしまうことにしかならない。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第1部 一般理論,2 実証主義と法・道徳分離論,pp.95-96,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),上山友一(訳),松浦好治(訳))
(索引:半影的問題)

(出典:wikipedia)
 「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
では要約に移りましょう。法学や哲学の将来に対する私の展望では、まだ終わっていない仕事がたくさんあります。私の国とあなたがたの国の両方で社会政策の実質的諸問題が個人の諸権利の観点から大いに議論されている時点で、われわれは、基本的人権およびそれらの人権と法を通して追求される他の諸価値との関係についての満足のゆく理論を依然として必要としているのです。したがってまた、もしも法理学において実証主義が最終的に葬られるべきであるとするならば、われわれは、すべての法体系にとって、ハード・ケースの解決の予備としての独自の正当化的諸原理群を含む、拡大された法の概念が、裁判官の任務の記述や遂行を曖昧にせず、それに照明を投ずるであろうということの論証を依然として必要としているのです。しかし現在進んでいる研究から判断すれば、われわれがこれらのものの少なくともあるものを手にするであろう見込みは十分あります。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第2部 アメリカ法理学,5 1776-1976年 哲学の透視図からみた法,pp.178-179,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),深田三徳(訳))
(索引:)
ハーバート・ハート(1907-1992)
ハーバート・ハートの関連書籍(amazon)
検索(ハーバート・ハート)


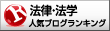
法律・法学ランキング
政治思想ランキング
 |
(出典:wikipedia)
 「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。では要約に移りましょう。法学や哲学の将来に対する私の展望では、まだ終わっていない仕事がたくさんあります。私の国とあなたがたの国の両方で社会政策の実質的諸問題が個人の諸権利の観点から大いに議論されている時点で、われわれは、基本的人権およびそれらの人権と法を通して追求される他の諸価値との関係についての満足のゆく理論を依然として必要としているのです。したがってまた、もしも法理学において実証主義が最終的に葬られるべきであるとするならば、われわれは、すべての法体系にとって、ハード・ケースの解決の予備としての独自の正当化的諸原理群を含む、拡大された法の概念が、裁判官の任務の記述や遂行を曖昧にせず、それに照明を投ずるであろうということの論証を依然として必要としているのです。しかし現在進んでいる研究から判断すれば、われわれがこれらのものの少なくともあるものを手にするであろう見込みは十分あります。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第2部 アメリカ法理学,5 1776-1976年 哲学の透視図からみた法,pp.178-179,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),深田三徳(訳))
(索引:)
ハーバート・ハート(1907-1992)
ハーバート・ハートの関連書籍(amazon)
検索(ハーバート・ハート)
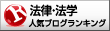
法律・法学ランキング

政治思想ランキング