言語の畜群的遠近法
【無意識に為される多くのことの極めて僅少で表面的な部分である意識的世界の、さらに小さな一部が、言語で表現された世界である。言語は、人と人を結びつける必要性に起源があり、畜群的遠近法とも言える歪みを持つ。(フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900))】
(1)意識のうちに入らずに為される多くのことがある。感覚、思考、情動、意欲、想起。
(2)また、我々の行為は、根本において比類ない仕方で個人的であり、唯一的であり、あくまでも個性的であることに疑いの余地がない。
(3)意識にのぼってくる思考は、意識されない思考の極めて僅少の部分、その最も表面的な部分、最も粗悪な部分にすぎない。
(4)さらに、言語で表現された世界は、意識にのぼってくるものの、さらに限定された一部である。しかもそれは、一般化され、凡俗化され、深みを失い、薄っぺらになり、愚劣となり、頽廃があり、偽造がある。
(5)自分自身をできるかぎり個的に理解しよう、「自己自身を知ろう」と望んでも、意識にのぼってくるのは、非個的なもの、「平均的なもの」、「種族の守護霊」によって多数決にかけられ、畜群的遠近法に訳し戻されたものである。結局のところ、増大する意識とは一つの危険であり、一つの病気とも言えるのである。
(6)以上のことは、意識と言語の以下のような起源に由来する。
(6.1)人間は、最も危険に曝された動物として、仲間の救助や保護を必要とした。
(6.2)仲間に知らせる必要のあることが、意識化され、言語化された。すなわち意識も言語も、種族、共同体的、畜群的な効用に関する点で、精妙な発達をとげてきた。なお、人と人を結びつけるものには、眼差しや身振りの働きもある。
(6.2.1)自分の危急状態、何が不足しているのか。
(6.2.2)自分がどんな気分でいるのか、何を考えているのか。
(6.2.3)人と人とを結びつける連絡網、特に命令者と服従者を結びつける。
「「種族の守護霊」について。
―――意識(もっと正しく言えば、自己を意識すること)の問題は、どの程度までわれわれは意識なしで済ませられるかを悟りだすときにはじめて、われわれの前面にあらわれてくる。
こうした悟り始めの地点に、今日われわれを立たせるのは、生理学と動物学とである(これらの学問は、したがって、ライプニッツの先駆的な疑問に追いつくのに二世紀かかったわけだ)。
すなわち、われわれは、考えたり、感じたり、欲したり、想い起こしたりすることができるし、同様にまた語のあらゆる意味で「行為する」ことができるだろう、だがそうだとしてもそうした一切のものがわれわれの「意識のうちに入ってくる」(比喩的に言われるごとく)ことを要しない筈だ。
生の全体は、それがいわば鏡に自分を映してみなくても、可能な筈である―――実際において今日でもなお、われわれにおけるこの生活の大半が、こうした鏡面映写なしに演じられているごとくに―――、しかもそこにわれわれの思考し・情感し・意欲する生をも含めての話だ、こう言えば老いぼれた哲学者の耳には侮辱したように聞こえるかもしれないけれど。
―――意識が大体において《余計なもの》であるとするなら、いったい意識は《何のため》にあるのか?
―――ところで、この問題に対する私の解答とその恐らくは的外れかもしれぬ推測に人々が耳を藉してくれるとしての話だが、意識の精緻さと強さとはつねに人間(あるいは動物)の《伝達能力》に比例し、またその伝達能力は《伝達の必要》に比例する、と私には思われる。
この後者の場合、自分の必要をひとに伝達したり分からせたりすることにかけては実に名人である当の個人それ自体が、その必要という点で同時にまた大抵のことを他人に頼らねばならないものだ、といった風にこれを解してはならない。
だがしかし、こと種族全体や血族連鎖の全体に関するかぎりでは、たしかにそんな風の事情になっているように、私には思われる。
必要とか困窮とかのために、長期にわたって人間が、伝達し合い相互に迅速かつ精細に理解しあうよう迫られたところでは、ついにあり余る程のこうした伝達の力と技が生じてくる。それはいわば漸次に蓄積された末にこれを浪費する相続人を待つばかりになっている資産のようなものである
(―――いわゆる芸術家はこうした意味の相続人であるし、演説家も説教家も著述家も同断である。これらの者はみな、きまって長い血族連鎖の最後にあらわれ、いつの場合も語の最上の意味での「末裔」であり、前述のようにその本質において「浪費家」である)。
この私の考察が正しいとしたら、さらに次のように推測をすすめることができよう、すなわち、《およそ意識というものは伝達の必要に迫られてのみ発達したものである》、―――もともとそれは人と人との間(特に命令者と服従者との間)にのみ必要なもの、有用なものであって、しかもこの有用性の程度に比例してのみ発達したものである、と。
意識とは、本来、人と人との間の連絡網にすぎない、―――ただそうしたものとしてのみ発達したに違いなかった。つまり、世捨人的な猛獣のような人間なら意識など必要とはしなかっただろう。
われわれの行為、想念、感情、運動すらも―――すくなくともそれらの一部分が―――われわれの意識にのぼってくるということは、長いあいだ人間を支配してきた恐るべき「やむなき必要」(Muss)の結果なのだ。
人間は、最も危険に曝された動物として、救助や保護を《必要とした》、人間は《同類を必要とした》、人間は自分の危急を言い表わし自分を分からせるすべを知らねばならなかった、―――こうしたすべてのことのために人間は何はおいてまず「意識」を必要とした、つまり自分に何が不足しているかを「知る」こと、自分がどんな気分でいるかを「知る」こと、自分が何を考えているかを「知る」ことが、必要であった。
なぜなら、もう一度言うが、人間は一切の生あるものと同じく絶えず考えてはいる、がそれを知らないでいるからである。
《意識にのぼって》くる思考は、その知られないでいる思考の極めて僅少の部分、いうならばその最も表面的な部分、最も粗悪な部分にすぎない。
―――というのも、この意識化された思考だけが、《言語をもって、すなわち伝達記号》―――これで意識の素性そのものがあばきだされるが―――《をもって営まれる》からである。
要すれば、言葉の発達と意識の発達(理性の発達では《なく》、たんに理性の自意識化の発達)とは、手を携えてすすむ。
付言すれば、人と人との間の橋渡しの役をはたすのは、ただたんに言葉だけではなく、眼差しや圧力や身振りもそうである。
われわれ自身における感覚印象の意識化、それらの印象を固定することができ、またいわばこれをわれわれの外に表出する力は、これら印象をば記号を媒介にして《他人に》伝達する必要が増すにつれて増大した。
記号を案出する人間は、同時に、いよいよ鋭く自分自身を意識する人間である。
人間は、社会的動物としてはじめて、自分自身を意識するすべを覚えたのだ、―――人間は今もってそうやっているし、いよいよそうやってゆくのだ。―――お察しのとおり、私の考えは、こうだ
―――意識は、もともと、人間の個的実存に属するものでなく、むしろ人間における共同体的かつ畜群的な本性に属している。従って理の当然として、意識はまた、共同体的かつ畜群的な効用に関する点でだけ、精妙な発達をとげてきた。
また従って、われわれのひとりびとりは、自分自身をできるかぎり個的に《理解し》よう、「自己自身を知ろう」と、どんなに望んでも、意識にのぼってくるのはいつもただ他ならぬ自分における非個的なもの、すなわち自分における「平均的なもの」だけであるだろう、
―――われわれの思想そのものが、たえず、意識の性格によって―――意識の内に君臨する「種族の守護霊」によって―――いわば《多数決にかけられ》、畜群的遠近法に訳し戻される。
われわれの行為は、根本において一つ一つみな比類ない仕方で個人的であり、唯一的であり、あくまでも個性的である、それには疑いの余地がない。
それなのに、われわれがそれらを意識に翻訳するやいなや、《それらはもうそう見えなくなる》・・・これこそが《私》の解する真の現象論であり遠近法論である。
《動物的意識》の本性の然らしめるところ、当然つぎのような事態があらわれる。すなわち、われわれに意識されうる世界は表面的世界にして記号世界であるにすぎない、一般化された世界であり凡俗化された世界にすぎない、
―――意識されるものの一切は、意識されるそのことによって深みを失い、薄っぺらになり、比較的に愚劣となり、一般化され、記号に堕し、畜群的標識に《化する》。すべて意識化というものには、大きなしたたかな頽廃が、偽造が、皮相化と一般化が、結びついている。
結局のところ、増大する意識とは一つの危険なのだ。そして、極度に意識的となったヨーロッパ人のあいだに生活する者は、その上それが一つの病気でもあることを知っている。
お察しのことだろうが、ここで私が問題としているのは、主観と客観の対立などではない。こんな区別だてなど、文法(俗流形而上学)の罠にかかったままでいる認識論者諸君の手に一任する。
ましてやそれは、「物自体」と現象との対立といったものではさらさらない。なぜなら、われわれの「認識」は、そうした《区別》だけでもやれるにはまだまだ遥かに不充分だからだ。
われわれは《認識》のための、「真理」のための器官を、全く何ひとつ有っていない。
われわれは、人間畜群や種族のために《有用だ》とされるちょうどそれだけを「知る」(あるいは信ずる・あるいは妄想する)のである。
しかも、ここで「有用」と呼ばれるものでさえも、所詮また一個の信仰、一個の妄想にすぎず、また恐らくそれこそは、われわれをいつかは破滅させるあの宿命的な蒙昧さであるかもしれない。」
(フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900)『悦ばしき知識』第五書、三五四、ニーチェ全集8 悦ばしき知識、pp.391-395、[信太正三・1994])
(索引:意識の発生,言語の起源,畜群的遠近法)

(出典:
wikipedia)

「精神も徳も、これまでに百重にもみずからの力を試み、道に迷った。そうだ、人間は一つの試みであった。ああ、多くの無知と迷いが、われわれの身において身体と化しているのだ!
幾千年の理性だけではなく―――幾千年の狂気もまた、われわれの身において突発する。継承者たることは、危険である。
今なおわれわれは、一歩また一歩、偶然という巨人と戦っている。そして、これまでのところなお不条理、無意味が、全人類を支配していた。
きみたちの精神と
きみたちの徳とが、きみたちによって新しく定立されんことを! それゆえ、きみたちは
戦う者であるべきだ! それゆえ、きみたちは
創造する者であるべきだ!
認識しつつ身体はみずからを浄化する。認識をもって試みつつ身体はみずからを高める。認識する者にとって、一切の衝動は聖化される。高められた者にとって、魂は悦ばしくなる。
医者よ、きみ自身を救え。そうすれば、さらにきみの患者をも救うことになるだろう。
自分で自分をいやす者、そういう者を目の当たり見ることこそが、きみの患者にとって最善の救いであらんことを。
いまだ決して歩み行かれたことのない
千の小道がある。生の
千の健康があり、生の
千の隠れた島々がある。人間と人間の大地とは、依然として汲みつくされておらず、また発見されていない。
目を覚ましていよ、そして耳を傾けよ、きみら孤独な者たちよ!
未来から、風がひめやかな羽ばたきをして吹いてくる。そして、さとい耳に、よい知らせが告げられる。
きみら今日の
孤独者たちよ、きみら
脱退者たちよ、きみたちはいつの日か一つの民族となるであろう。―――そして、この民族からして、超人が〔生ずるであろう〕。
まことに、大地はいずれ治癒の場所となるであろう! じじつ大地の周辺には、早くも或る新しい香気が漂っている。治癒にききめのある香気が、―――また或る新しい希望が〔漂っている〕!」
(フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900)『このようにツァラトゥストラは語った』第一部、(二二)贈与する徳について、二、ニーチェ全集9 ツァラトゥストラ(上)、pp.138-140、[吉沢伝三郎・1994])
フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900)
ニーチェの関連書籍(amazon)

検索(ニーチェ)

 心理学ランキング
ブログサークル
心理学ランキング
ブログサークル

 「あなたが宇宙を任されていて、知性と感覚を備えたあらたな種を創造しようと決意したとする。この種はこれから、地球のように資源が乏しい世界で暮らす。そこは、資源を「持てる者」に分配するのではなく「持たざる者」へ分配することによって、より多くの苦しみが取り除かれ、より多くの幸福が生み出される世界だ。あなたはあらたな生物の心の設計にとりかかる。そして、その生物が互いをどう扱うかを選択する。あなたはあらたな種の選択肢を次の三つに絞った。
「あなたが宇宙を任されていて、知性と感覚を備えたあらたな種を創造しようと決意したとする。この種はこれから、地球のように資源が乏しい世界で暮らす。そこは、資源を「持てる者」に分配するのではなく「持たざる者」へ分配することによって、より多くの苦しみが取り除かれ、より多くの幸福が生み出される世界だ。あなたはあらたな生物の心の設計にとりかかる。そして、その生物が互いをどう扱うかを選択する。あなたはあらたな種の選択肢を次の三つに絞った。

 「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。
「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。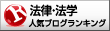

 「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。

 「精神も徳も、これまでに百重にもみずからの力を試み、道に迷った。そうだ、人間は一つの試みであった。ああ、多くの無知と迷いが、われわれの身において身体と化しているのだ!
「精神も徳も、これまでに百重にもみずからの力を試み、道に迷った。そうだ、人間は一つの試みであった。ああ、多くの無知と迷いが、われわれの身において身体と化しているのだ!

 「バナナに手をのばすことならどんな類人猿にもできるが、星に手をのばすことができるのは人間だけだ。類人猿は森のなかで生き、競いあい、繁殖し、死ぬ――それで終わりだ。人間は文字を書き、研究し、創造し、探究する。遺伝子を接合し、原子を分裂させ、ロケットを打ち上げる。空を仰いでビッグバンの中心を見つめ、円周率の数字を深く掘り下げる。なかでも並はずれているのは、おそらく、その目を内側に向けて、ほかに類のない驚異的なみずからの脳のパズルをつなぎあわせ、その謎を解明しようとすることだ。まったく頭がくらくらする。いったいどうして、手のひらにのるくらいの大きさしかない、重さ3ポンドのゼリーのような物体が、天使を想像し、無限の意味を熟考し、宇宙におけるみずからの位置を問うことまでできるのだろうか? とりわけ畏怖の念を誘うのは、その脳がどれもみな(あなたの脳もふくめて)、何十億年も前にはるか遠くにあった無数の星の中心部でつくりだされた原子からできているという事実だ。何光年という距離を何十億年も漂ったそれらの粒子が、重力と偶然によっていまここに集まり、複雑な集合体――あなたの脳――を形成している。その脳は、それを誕生させた星々について思いを巡らせることができるだけでなく、みずからが考える能力について考え、不思議さに驚嘆する自らの能力に驚嘆することもできる。人間の登場とともに、宇宙はにわかに、それ自身を意識するようになったと言われている。これはまさに最大の謎である。」
「バナナに手をのばすことならどんな類人猿にもできるが、星に手をのばすことができるのは人間だけだ。類人猿は森のなかで生き、競いあい、繁殖し、死ぬ――それで終わりだ。人間は文字を書き、研究し、創造し、探究する。遺伝子を接合し、原子を分裂させ、ロケットを打ち上げる。空を仰いでビッグバンの中心を見つめ、円周率の数字を深く掘り下げる。なかでも並はずれているのは、おそらく、その目を内側に向けて、ほかに類のない驚異的なみずからの脳のパズルをつなぎあわせ、その謎を解明しようとすることだ。まったく頭がくらくらする。いったいどうして、手のひらにのるくらいの大きさしかない、重さ3ポンドのゼリーのような物体が、天使を想像し、無限の意味を熟考し、宇宙におけるみずからの位置を問うことまでできるのだろうか? とりわけ畏怖の念を誘うのは、その脳がどれもみな(あなたの脳もふくめて)、何十億年も前にはるか遠くにあった無数の星の中心部でつくりだされた原子からできているという事実だ。何光年という距離を何十億年も漂ったそれらの粒子が、重力と偶然によっていまここに集まり、複雑な集合体――あなたの脳――を形成している。その脳は、それを誕生させた星々について思いを巡らせることができるだけでなく、みずからが考える能力について考え、不思議さに驚嘆する自らの能力に驚嘆することもできる。人間の登場とともに、宇宙はにわかに、それ自身を意識するようになったと言われている。これはまさに最大の謎である。」



