情念論
《概要》
・
わたしたちは、情念を巧みに操縦し、その引き起こす悪を十分耐えやすいものにし、情念のすべてから喜びを引き出すような知恵を持つことができる。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
情念はその本性上すべて善い、その悪用法や過剰を避けるだけでよい。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
情念は、わたしたちを害したり益したりしうる対象の多様なしかたを反映している。(ルネ・デカルト(1596-1650))
《改訂履歴》
2019/7/22 第1版
情念論
《目次》
1
〈驚き〉
1.1〈驚き〉の過剰としての
〈恐怖〉
1.2 大きいものへの〈驚き〉:
〈重視〉
1.3 小さいものへの〈驚き〉:
〈軽視〉
1.4 〈善〉または〈悪〉をなしうる自由な原因への〈重視〉:
〈崇敬〉
1.5 〈善〉または〈悪〉をなしうる自由な原因への〈軽視〉:
〈軽蔑〉
※ 〈善〉〈悪〉については、後述する。
2
〈快〉と
〈嫌悪〉
2.1
〈美〉と
〈美への愛〉(快)
2.2
〈醜〉と
〈醜への憎しみ〉(嫌悪)
2.3
〈広義の美〉と
〈美への愛〉(快)
2.4
〈広義の醜〉と
〈醜への憎しみ〉(嫌悪)
2.5
〈善〉と
〈善への愛〉
2.6
〈悪〉と
〈悪への憎しみ〉
3 わたしたちの状況・行為、他の人たちの状況・行為による〈善〉〈悪〉の感受
3.1 わたしたちの
現在の状況による〈善〉と〈悪〉の感受:
〈喜び〉〈悲しみ〉
3.2 わたしたちの
未来による〈善〉と〈悪〉の感受:
〈欲望〉
3.3 わたしたち自身によって過去なされた行為による〈善〉と〈悪〉の感受:
〈内的自己満足〉〈後悔〉
3.4 わたしたち自身によって過去なされた行為や現在のわたしたちに関する、
他の人たちの意見による〈善〉と〈悪〉の感受:
〈誇り〉〈恥〉
3.5 他の人たちによってなされた行為による〈善〉と〈悪〉の感受:
〈好意〉〈感謝〉〈憤慨〉〈怒り〉
3.6 他の人たちの現在の状況や未来に生じる状況による〈善〉と〈悪〉の感受:
〈喜び〉〈うらやみ〉〈笑いと嘲り〉〈憐れみ〉
3.7 その他の〈善〉と〈悪〉の感受:
〈倦怠〉〈いやけ〉〈心残り〉〈爽快〉
4 〈善〉〈悪〉〈美〉〈醜〉と、情念の関係
5 真なる〈善〉〈悪〉、偽なる〈善〉〈悪〉にもとづく情念
6 さまざまな〈愛〉による〈美〉〈広義の美〉〈善〉の感受
6.1 〈美〉と〈美への愛〉(快) (再掲)
6.2 〈広義の美〉と〈美への愛〉(快) (再掲)
6.3 〈善〉と〈善への愛〉 (再掲)
6.4
〈欲情の愛〉〈好意の愛〉による〈美〉〈広義の美〉〈善〉の感受。
6.5
〈所有への愛〉〈対象そのものへの愛〉による〈美〉〈広義の美〉〈善〉の感受。
6.6
〈愛着〉〈友愛〉〈献身〉による〈美〉〈広義の美〉〈善〉の感受。
7 欲望論
7.1 わたしたちの未来による〈善〉と〈悪〉の感受:〈欲望〉 (再掲)
7.2〈欲望〉の種類
7.3
〈安心〉〈希望〉〈不安〉〈執着〉〈絶望〉〈恐怖〉
8 自由意志論
9 徳
9.1 欲望は、真なる認識に従っているか
9.2 私たちに依存しないもの
9.3 私たちにのみ依存するもの、自由意志
9.4 意思決定に付随する情念:
〈不決断〉〈大胆〉〈勇気〉〈対抗心〉〈臆病〉〈恐怖〉
9.5 過去の意思決定に付随する情念:
〈良心の悔恨〉
9.6 徳とは何か?
9.7 徳に伴う情念、知的な〈喜び〉〈高邁〉、その反対の〈卑屈〉
9.8 〈高邁〉の情念をもつ人々の関係
9.9 〈高邁〉とは異なる
〈高慢〉
1
〈驚き〉
・
「驚き」に不意を打たれ、激しく揺り動かさるとき、そこには既知ではない、想定外の、初めて出会う新しい対象が存在する。驚きが、知らなかったことを学ばせ、記憶にとどめさせる。(ルネ・デカルト(1596-1650))
(出典:
wikipedia)

1.1〈驚き〉の過剰としての
〈恐怖〉
生物的準備性の例:ヘビ、クモ、血、嵐、高所、暗闇、見知らぬ人への恐怖、言語の獲得、数学的な技能、音楽の観賞、空間知覚。(スティーブン・ピンカー(1954-))

(出典:
wikipedia)
検索(スティーブン・ピンカー)
1.2 大きいものへの〈驚き〉:
〈重視〉
1.3 小さいものへの〈驚き〉:
〈軽視〉
・
〈重視〉と〈軽視〉(ルネ・デカルト(1596-1650))
1.4 〈善〉または〈悪〉をなしうる自由な原因への〈重視〉:
〈崇敬〉
1.5 〈善〉または〈悪〉をなしうる自由な原因への〈軽視〉:
〈軽蔑〉
・
〈崇敬〉と〈軽蔑〉(ルネ・デカルト(1596-1650))
※ 〈善〉〈悪〉については、後述する。
・
崇敬とは、愛や献身とは異なり、善または悪をなしうる驚くべき大きな自由原因に対し、その対象から好意を得ようと努め何らかの不安を持って、その対象に服従しようとする、精神の傾向だ。(ルネ・デカルト(1596-1650))
※ 〈愛〉〈献身〉については、後述する。
2
〈快〉と
〈嫌悪〉
・
美、広義の美、美への愛(快)、醜、広義の醜、醜への憎しみ(嫌悪)、善、善への愛、悪、悪への憎しみ。快と嫌悪の情念は、他の種類の愛や憎しみより、通例いっそう強烈であり、また欺くこともある。(ルネ・デカルト(1596-1650))
2.1
〈美〉と
〈美への愛〉(快)
視覚で与えられた対象に「快」を感じるとき、そこには私たちの本性に適するであろう何かが存在する。それが本性に適するものであるとき、それが〈美〉であり、この快の情動を、〈美への愛〉という。快を感じさせるすべてのものが〈美〉であるわけではない。「それらはふつう、真理性がより少ない。したがって、あらゆる情念のうちで、最も欺くもの、最も注意深く控えるべきものは、これらの情念である。」情動と〈美〉とのこの関係性は、以下、情動と〈醜〉、〈善〉、〈悪〉との関係においても同様である。快と嫌悪の情念は、他の種類の愛や憎しみより、通例いっそう強烈である。なぜなら、感覚が表象して精神にやってくるものは、理性が表象するものよりも強く精神を刺激するからである。
2.2
〈醜〉と
〈醜への憎しみ〉(嫌悪)
視覚で与えられた対象に「嫌悪」ないし「嫌忌」を感じるとき、そこには私たちの本性を害するであろう何かが存在する。
2.3
〈広義の美〉と
〈美への愛〉(快)
※〈特殊感覚〉のうち聴覚、嗅覚、味覚、平衡覚、〈表在性感覚〉(皮膚の触覚、圧覚、痛覚、温覚)、〈深部感覚〉(筋、腱、骨膜、関節の感覚)、〈内臓感覚〉(空腹感、満腹感、口渇感、悪心、尿意、便意、内臓痛など)、「精神の能動によらない想像、夢の中の幻覚や、目覚めているときの夢想」によって、快の情動がもたらされる場合。
2.4
〈広義の醜〉と
〈醜への憎しみ〉(嫌悪)
※2.3と同様。
2.5
〈善〉と
〈善への愛〉
意志に依存するいっさいの想像、思考や理性がとらえた対象に「快」を感じるとき、そこには私たちの本性に適するであろう何かが存在する。それが本性に適するものであるとき、それが〈善〉であり、この快の情動を、〈善への愛〉という。快を感じさせるすべてのものが〈善〉であるわけではない。
2.6
〈悪〉と
〈悪への憎しみ〉
意志に依存するいっさいの想像、思考や理性がとらえた対象に「嫌悪」ないし「嫌忌」を感じるとき、そこには私たちの本性を害するであろう何かが存在する。
3
わたしたちの状況・行為、他の人たちの状況・行為による〈善〉〈悪〉の感受
3.1
わたしたちの現在の状況による〈善〉と〈悪〉の感受:〈喜び〉〈悲しみ〉
・
〈喜び〉、〈悲しみ〉(ルネ・デカルト(1596-1650))
わたしたちの現在の状況が「喜び」を感じさせるとき、そこには私たちの本性に適するであろう何かが存在する。それが本性に適するものであるとき、それは〈善〉である。また、「悲しみ」を感じさせるとき、そこには私たちの本性を害するであろう何かが存在する。それが本性を害するものであるとき、それは〈悪〉である。
私の信念である「私の自己像」
自己に関する概念のタイプ:現実自己、理想自己、あるべき自己に関する信念。特定の重要他者が考えているであろう現実自己、理想自己、あるべき自己に関する自分自身の想定。(E・トーリー・ヒギンズ(1946-))
(1a) 私(現実自己):私の信念である、私が実際に持っている属性。
(1b) 私(理想自己):私の信念である、私が理想として持ちたい属性。
(1c) 私(あるべき自己):私の信念である、私が持つべき属性。

(出典:
Social Psychology Network)
検索(E・トーリー・ヒギンズ)
現在の状況が感じさせる「落胆および不満」と「罪悪感および自己卑下」が、理想自己、あるべき自己を暗示する。「恥および当惑」と「恐れおよび危機感」が、特定の重要他者が考えると想定している理想自己、あるべき自己を暗示する。(E・トーリー・ヒギンズ(1946-))
(a)「落胆および不満」を感じるとき、私(理想自己)と私(現実自己)とに不一致がある。
(b)「罪悪感および自己卑下」を感じるとき、私(あるべき自己)と私(現実自己)とに不一致がある。
3.2
わたしたちの未来による〈善〉と〈悪〉の感受:〈欲望〉
・
〈欲望〉(ルネ・デカルト(1596-1650))
わたしたち自身の現在の状況が、「喜び」を感じさせるとき、未来においてもそれを保存しようと「欲望」されるとき、そこには、私たちの本性に適するであろう何かが存在する。それが本性に適するものであるとき、それは〈善〉である。(
善の保存の欲望)
わたしたち自身の現在の状況が、「悲しみ」を感じさせるとき、未来においてはそれを無くそうと「欲望」されるとき、そこには、私たちの本性を害するであろう何かが存在する。それが本性を害するものであるとき、それは〈悪〉である。(
悪の不在の欲望、改善の欲望)
わたしたち自身の予測される未来が、避けるべき未来として「欲望」されるとき、そこには私たちの本性を害するであろう何かが存在する。それが本性を害するものであるとき、それは〈悪〉である。(
悪の回避の欲望)
わたしたち自身のめざすべき未来が、新たな未来の獲得として「欲望」されるとき、このめざすべき未来には私たちの本性に適するであろう何かが存在する。それが本性に適するものであるとき、それは〈善〉である。(
善の獲得の欲望)
3.3
わたしたち自身によって過去なされた行為による〈善〉と〈悪〉の感受:〈内的自己満足〉〈後悔〉
・
〈内的自己満足〉、〈後悔〉、後悔の効用(ルネ・デカルト(1596-1650))
意志に依存する想像、思考や理性がとらえた、わたしたち自身によって過去なされたことが、「内的自己満足」を感じさせるとき、そこには私たちの本性に適するであろう何かが存在する。それが本性に適するものであるとき、それは〈善〉である。また、わたしたち自身によって過去なされたことが、「後悔」を感じさせるとき、そこには私たちの本性を害するであろう何かが存在する。それが本性を害するものであるとき、それは〈悪〉である。
人は、自己評価基準を持っており、これにより自己を査定、評価し、これに合わせて自己賞賛や自己非難、報酬や罰を自分自身に与えることができる。(アルバート・バンデューラ(1925-))

(出典:
wikipedia)
検索(アルバート・バンデューラ)
3.4
わたしたち自身によって過去なされた行為や現在のわたしたちに関する、他の人たちの意見による〈善〉と〈悪〉の感受:〈誇り〉〈恥〉
・
〈誇り〉、〈恥〉(ルネ・デカルト(1596-1650))
わたしたち自身によって過去なされたことについての、または現在のわたしたち自身についての、他の人たちが持ちうる意見を考えるときに「誇り」を感じさせるとき、そこには私たちの本性に適するであろう何かが存在する。それが本性に適するものであるとき、それは〈善〉である。また、他の人たちが持ちうる意見を考えるときに「恥」を感じさせるとき、そこには私たちの本性を害するであろう何かが存在する。それが本性を害するものであるとき、それは〈悪〉である。
・
誇りは希望によって徳へ促し、恥は不安によって徳へ促す。また仮に、真の善・悪でなくとも、世間の人たちの非難、賞賛は十分に考慮すること。(ルネ・デカルト(1596-1650))
私の想定である、特定の重要他者が持つ「私の自己像」
自己に関する概念のタイプ:現実自己、理想自己、あるべき自己に関する信念。特定の重要他者が考えているであろう現実自己、理想自己、あるべき自己に関する自分自身の想定。(E・トーリー・ヒギンズ(1946-))
(2a) 私(他者(現実自己)):特定の重要他者が持つと私が想定する、私が実際に持っている属性。
(2b) 私(他者(理想自己)):特定の重要他者が持つと私が想定する、私が理想として持ちたい属性。
(2c) 私(他者(あるべき自己)):特定の重要他者が持つと私が想定する、私が持つべき属性。
※注意:下記とは異なる。
特定の重要他者が実際に持つ「私の自己像」
(3a) 他者(現実自己):特定の重要他者が実際に持つ、私が実際に持っている属性。
(3b) 他者(理想自己):特定の重要他者が実際に持つ、私が理想として持ちたい属性。
(3c) 他者(あるべき自己):特定の重要他者が実際に持つ、私が持つべき属性。

(出典:
Social Psychology Network)
検索(E・トーリー・ヒギンズ)
現在の状況が感じさせる「落胆および不満」と「罪悪感および自己卑下」が、理想自己、あるべき自己を暗示する。「恥および当惑」と「恐れおよび危機感」が、特定の重要他者が考えると想定している理想自己、あるべき自己を暗示する。(E・トーリー・ヒギンズ(1946-))
(a)「恥および当惑」を感じるとき、私(他者(理想自己))と私(現実自己)とに不一致がある。
(b)「恐れおよび危機感」を感じるとき、私(他者(あるべき自己))と私(現実自己)とに不一致がある。
特定の重要他者に自分の行為が知られずとも、恥を感じ恐れを感じるパーソナリティは、上記の機構で恥を感じ、恐れを感じているだろう。しかし、私(他者(理想自己))と私(理想自己)との相違、私(他者(あるべき自己))と私(あるべき自己)の相違を自覚している場合には、「恥および当惑」「恐れおよび危機感」を感じる機構も、異なってくるだろう。
(a')「恥および当惑」を感じるとき、私(他者(理想自己))と私(他者(現実自己))とに不一致がある。
(b')「恐れおよび危機感」を感じるとき、私(他者(あるべき自己))と私(他者(現実自己))とに不一致がある。
すなわち、ここでは私(現実自己)と私(他者(現実自己))の違いも、明確に自覚されているのである。他者が介在する情念「恥および当惑」「恐れおよび危機感」が、その人の真実の私(現実自己)や私(理想自己)、私(あるべき自己)を素通りしてしまう理由でもある。
一般的に誇りや恥は、達成の結果つまり失敗や成功が、内的に帰属されるときに最大化され、外的に帰属されるときに最小化される。(バーナード・ウェイナー(1935-))

(出典:
ResearchGate)
検索(バーナード・ウェイナー)
検索(Bernard Weiner)
3.5
他の人たちによってなされた行為による〈善〉と〈悪〉の感受:〈好意〉〈感謝〉〈憤慨〉〈怒り〉
・
〈好意〉、〈感謝〉(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
〈憤慨〉、〈怒り〉(ルネ・デカルト(1596-1650))
意志に依存する想像、思考や理性がとらえた、他の人たちによってなされた行為が、「好意」を感じさせるとき、またその行為がわたしたちに対してなされ「感謝」を感じさせるとき、そこには私たちの本性に適するであろう何かが存在する。それが本性に適するものであるとき、それは〈善〉である。
意志に依存する想像、思考や理性がとらえた、他の人たちによってなされた行為が、「憤慨」を感じさせるとき、またその行為がわたしたちに対してなされ「怒り」を感じさせるとき、そこには私たちの本性を害するであろう何かが存在する。それが本性を害するものであるとき、それは〈悪〉である。
・
怒りの効用、および怒りの治療法(ルネ・デカルト(1596-1650))
3.6
他の人たちの現在の状況や未来に生じる状況による〈善〉と〈悪〉の感受:〈喜び〉〈うらやみ〉〈笑いと嘲り〉〈憐れみ〉
・
〈喜び〉、〈うらやみ〉、〈笑いと嘲り〉、〈憐れみ〉(ルネ・デカルト(1596-1650))
他の人たちの現在の状況や未来に生じる状況が「喜び」や「うらやみ」を感じさせるとき、そこには私たちの本性に適するであろう何かが存在する。それが本性に適するものであるとき、それは〈善〉である。この〈善〉が、その人たちにふさわしいか、ふさわしくないかに応じて、「喜び」または「うらやみ」を感じる。
また、「笑いと嘲り」や「憐れみ」を感じさせるとき、そこには私たちの本性を害するであろう何かが存在する。それが本性を害するものであるとき、それは〈悪〉である。この〈悪〉が、その人たちにふさわしいか、ふさわしくないかに応じて、「笑いと嘲り」または「憐れみ」を感じる。
3.7
その他の〈善〉と〈悪〉の感受:〈倦怠〉〈いやけ〉〈心残り〉〈爽快〉
・
〈倦怠〉、〈いやけ〉、〈心残り〉、〈爽快〉(ルネ・デカルト(1596-1650))
4
〈善〉〈悪〉〈美〉〈醜〉と、情念の関係
・
善・悪、美・醜には真・偽の区別があり、経験と理性を用いて認識することができる。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
問題:(1)善を完全に知るには、無限といえるほどの知識が必要ではないか。(2)善の評価には、他の人の有益性も考慮すべきか。(3)他人の有益性の考慮がその人の性向だとしたら、違う人には違う「善」が完全だと承認させるのではないか。(エリーザベト・フォン・デア・プファルツ(1618-1680))

(出典:
wikipedia)
解答:(1)自己の傾向性に多くを任せ、自己の良心を満足させれば十分である。(2)この世界と個人の真実を知れば、全体の共通の善も認識できる。(3)仮に自己利益の考慮のみでも、思慮を用いて行為すれば共通の善も実現される。但し、道徳が腐敗していない時代に限る。(ルネ・デカルト(1596-1650))
5
真なる〈善〉〈悪〉、偽なる〈善〉〈悪〉にもとづく情念
・
自分に欠けている真理を知ることが、悲しみをもたらし不利益であったとしても、それを知らないことよりもより大きな完全性である。(ルネ・デカルト(1596-1650))
5.1 真なる〈善〉への〈愛〉〈喜び〉〈欲望〉〈内的自己満足〉〈誇り〉〈好意〉〈感謝〉〈喜び〉〈うらやみ〉、真なる〈美〉による〈快〉
・
善への愛と悪への憎しみが、真の認識にもとづくとき、愛は憎しみよりも比較にならないほど善い。(ルネ・デカルト(1596-1650))
5.2 真なる〈悪〉への〈憎しみ〉〈悲しみ〉〈欲望〉〈後悔〉〈恥〉〈憤慨〉〈怒り〉〈笑いと嘲り〉〈憐れみ〉、真なる〈醜〉による〈嫌悪〉
・
悲しみと憎しみは、喜びと愛よりも不可欠である。なぜなら、害を斥けるほうが、より完全性を加えてくれるものを獲得するよりも、いっそう重要だからだ。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
悪への憎しみは、真の認識に基づくときでも、やはり必ず有害である。なぜなら、この場合でも善への愛より行為することがつねに可能であるし、人における悪は善と結合しているからだ。(ルネ・デカルト(1596-1650))
5.3 偽なる〈善〉への〈愛〉〈喜び〉〈欲望〉〈内的自己満足〉〈誇り〉〈好意〉〈感謝〉〈喜び〉〈うらやみ〉、偽なる〈美〉による〈快〉
・
不十分な根拠にもとづく場合であっても、喜びや愛は、悲しみや憎しみよりも望ましい。しかし、偽なる善への愛は、害をなしうるものへ、わたしたちを結びつけてしまう。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
情念が、欲望を介して行動や生活態度を導く場合には、原因が誤りである情念はすべて有害である。特に、偽なる喜びは、偽なる悲しみよりも有害である。(ルネ・デカルト(1596-1650))
脅威を無視することができない状況にならない限り、否定的な自己関連情報の選択的注意により、肯定的で社会的に望ましい自己像を一貫して維持し、自己高揚的な肯定バイアスを持つことは、きわめて適応的で精神的に健康なパーソナリティである。(ウォルター・ミシェル(1930-))

(出典:
COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK)
精神的健康には、肯定的な自己像が必要である。もちろん、現実と全く異なるものは害悪であるが、仮にそれが、現実よりいくらか過度であっても、肯定的なことが必要である。逆に、事実でも否定的なら、低い自尊心や抑うつ傾向がみられやすい。(ウォルター・ミシェル(1930-))
5.4 偽なる〈悪〉への〈憎しみ〉〈悲しみ〉〈欲望〉〈後悔〉〈恥〉〈憤慨〉〈怒り〉〈笑いと嘲り〉〈憐れみ〉、偽なる〈醜〉による〈嫌悪〉
6
さまざまな〈愛〉による〈美〉〈広義の美〉〈善〉の感受
6.1
〈美〉と
〈美への愛〉(快) (再掲)
視覚で与えられた対象に「快」を感じるとき、そこには私たちの本性に適するであろう何かが存在する。それが本性に適するものであるとき、それが〈美〉であり、この快の情動を、〈美への愛〉という。
6.2
〈広義の美〉と
〈美への愛〉(快) (再掲)
※〈特殊感覚〉のうち聴覚、嗅覚、味覚、平衡覚、〈表在性感覚〉(皮膚の触覚、圧覚、痛覚、温覚)、〈深部感覚〉(筋、腱、骨膜、関節の感覚)、〈内臓感覚〉(空腹感、満腹感、口渇感、悪心、尿意、便意、内臓痛など)、「精神の能動によらない想像、夢の中の幻覚や、目覚めているときの夢想」によって、快の情動がもたらされる場合。
6.2.1 有能性への欲望
有能性への欲望:私たちには、活動それ自体を楽しみ、その効力感を感じ、有能性を獲得し効果的に機能すること、課題に習熟することへの欲求がある。例として、好奇心、刺激への欲求、遊び、冒険への欲求。(ロバート・W・ホワイト(1904-2001))
検索(Robert W. White)
検索(ロバート・W・ホワイト)
6.2.2 〈快〉の原因となりうる様々な知覚の一覧
(以下、5.2 再掲)
5.2
あらゆる種類の知覚ないし認識が、一般に精神の受動である。
5.2.1
身体を原因とする知覚
5.2.1.1
外部感覚
・
対象に注意を向けるのは能動であるにしても、外部感覚は精神の受動である。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・〈特殊感覚〉視覚、聴覚、嗅覚、味覚、平衡覚
6.2.2.1 感覚的な遊びが〈芸術〉である。
5.2.1.2
共通感覚
・
ある特定の外部感覚は、その原因となる身体の能動が、より広い範囲の身体に影響を与え、これら身体の能動を精神において受動する共通感覚を生じる。(ルネ・デカルト(1596-1650))
5.2.1.3
想像力、記憶
・
外部感覚だけでなく、それがより広い範囲の身体に影響を与えて生じた共通感覚もまた、記憶され、想像力の対象となる。(ルネ・デカルト(1596-1650))
5.2.1.4
自分の肢体のなかにあるように感じる痛み、熱さ、その他の変様
・〈表在性感覚〉皮膚の触覚、圧覚、痛覚、温覚
・〈深部感覚〉筋、腱、骨膜、関節の感覚
・
精神の受動のひとつ、身体ないしその一部に関係づける知覚として、飢え、渇き、その他の自然的欲求、自分の肢体のなかにあるように感じる痛み、熱さ、その他の変様がある。(ルネ・デカルト(1596-1650))
5.2.1.5
身体ないしその一部に関係づける知覚としての、飢え、渇き、その他の自然的欲求 ・〈内臓感覚〉空腹感、満腹感、口渇感、悪心、尿意、便意、内臓痛など
5.2.1.6
精神の能動によらない想像、夢の中の幻覚や、目覚めているときの夢想(広い意味では、情念の一種)
・
精神の受動のひとつ、身体によって起こる知覚として、意志によらない想像がある。夢の中の幻覚や、目覚めているときの夢想も、これである。これらは、飢え、渇き、痛みとは異なり、精神に関連づけられており、これらは情念の一種である。(ルネ・デカルト(1596-1650))
5.2.2
精神を原因とする知覚
・
意志についての知覚、意志に依存するいっさいの想像や他の思考についての知覚は、知覚ということからは精神の受動であるが、精神から見れば能動である。(ルネ・デカルト(1596-1650))
5.2.2.1
意志についての知覚
5.2.2.2
意志に依存するいっさいの想像や他の思考についての知覚
(以下、5.1 再掲)
5.1
意志のすべてが精神の能動である。
5.1.1
精神そのもののうちに終結する精神の能動
・
意志のひとつとして、精神そのもののうちに終結する精神の能動がある。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
認識力は、想像力と共同して外部感覚や共通感覚に働きかけるときは認知と呼ばれ、記憶をもとにした想像力だけに働きかけるときは想起と呼ばれ、新たな形をつくるために想像力に働きかけるときは想像と呼ばれ、独りで働くときは理解(純粋悟性)と呼ばれる。(ルネ・デカルト(1596-1650))
5.1.1.1 「見る」とか「触れる」等の
認知とは
認識力が、想像力と共同して外部感覚や共通感覚に働きかけること。
5.1.1.2 記憶の「
想起」とは
認識力が、記憶をもとにした想像力だけに働きかけること。
5.1.1.3 「
想像する」とか「
表象する」こととは
認識力が、新たな形をつくるために想像力に働きかけること。
(例)存在しない何かを想像する。
・
存在しない何かを想像しようと努める場合、また、可知的なだけで想像不可能なものを考えようと努める場合、こうしたものについての精神の知覚も主として、それらを精神に知覚させる意志による。(ルネ・デカルト(1596-1650))
(例)詩人は、精神的なものを形象化するために、想像力を用いる。
・
悟性は精神的なものを形象化するために、風や光などのようなある種の感覚的物体も、用いることができる。これは詩人たちの手法だ。(ルネ・デカルト(1596-1650))
5.1.1.4 「
理解する」こと(
純粋悟性)とは
認識力が、独りで働くこと。
(例)可知的なだけで想像不可能なものを考える。
・
悟性はいかにして、想像力、感覚、記憶から助けられ、あるいは妨げられるか。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
悟性は、感覚でとらえ得ないものを理解するときは、かえって想像力に妨げられる。逆に、感覚的なものの場合は、観念を表現する物自体(モデル)を作り、本質的な属性を抽象し、物のある省略された形(記号)を利用する。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
問題となっている対象を表わす抽象化された記号を、紙の上の諸項として表現する。次に紙の上で、記号をもって解決を見出すことで、当初の問題の解を得る。(ルネ・デカルト(1596-1650))
(例)捨象、抽象
6.2.2.2 知的な遊びが〈学問〉である。
5.1.2
身体において終結する精神の能動(運動、行動)
・
意志のひとつとして、身体において終結する能動がある。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
想像が、多数のさまざまな運動の原因となる。(ルネ・デカルト(1596-1650))
(例)観念を表現する物自体(モデル)
(例)物のある省略された形(記号)
(例)問題となっている対象を表わす抽象化された記号を、紙の上の諸項として表現する。
6.2.2.3 身体的な遊びが〈スポーツ〉である。
6.3
〈善〉と
〈善への愛〉 (再掲)
意志に依存するいっさいの想像、思考や理性がとらえた対象に「快」を感じるとき、そこには私たちの本性に適するであろう何かが存在する。それが本性に適するものであるとき、それが〈善〉であり、この快の情動を、〈善への愛〉という。
6.4
〈欲情の愛〉〈好意の愛〉による〈美〉〈広義の美〉〈善〉の感受。
・
〈欲情の愛〉、〈好意の愛〉(ルネ・デカルト(1596-1650))
ある対象に「欲望」を感じるとき、それは、私たちの本性に適するであろう対象である。それが本性に適するものであるとき、その対象は〈美〉〈広義の美〉〈善〉であり、この情動は〈愛〉の一つの種類である。
ある対象に「好意」を感じ、その対象のために〈善〉を意志することを促されるとき、それは、私たちの本性に適するであろう対象である。それが本性に適するものであるとき、その対象は〈善〉であり、この情動は〈愛〉の一つの種類である。
6.5
〈所有への愛〉〈対象そのものへの愛〉による〈美〉〈広義の美〉〈善〉の感受。
・
〈所有への愛〉、〈対象そのものへの愛〉(ルネ・デカルト(1596-1650))
ある対象を「所有したい」と感じるとき、それは、私たちの本性に適するであろう対象である。それが本性に適するものであるとき、その対象は〈美〉〈広義の美〉〈善〉であり、この情動は〈愛〉の一つの種類である。例として、野心家が求める栄誉、主銭奴が求める金銭、酒飲みが求める酒、獣的な者が求める女。
ある対象を第二の自己自身と考えて、その対象にとっての〈善〉を自分の〈善〉のごとく求めるとき、あるいはそれ以上の気遣いをもって求めるとき、それは、私たちの本性に適するであろう対象である。それが本性に適するものであるとき、その対象は〈善〉であり、この情動は〈愛〉の一つの種類である。例として、有徳な人にとっての友人、よき父にとっての子供たち。
6.6
〈愛着〉〈友愛〉〈献身〉による〈美〉〈広義の美〉〈善〉の感受。
・
〈愛着〉、〈友愛〉、〈献身〉(ルネ・デカルト(1596-1650))
ある対象に「愛着」を感じるとき、それは、自分以下に評価されている、私たちの本性に適するであろう対象である。それが本性に適するものであるとき、その対象は〈美〉〈広義の美〉〈善〉であり、この情動は〈愛〉の一つの種類である。例として、一つの花、一羽の鳥、一頭の馬。
ある対象に「友愛」を感じるとき、それは、自分と同等に評価されている、私たちの本性に適するであろう対象である。それが本性に適するものであるとき、その対象は〈善〉であり、この情動は〈愛〉の一つの種類である。例として、自分が真にけだかく高邁な精神を持つと考え、また仮に、相手が不完全であると考えても、その相手に対してきわめて完全な友愛を持ちえないことはない。
ある対象に「献身」を感じるとき、それは、自分よりも高く評価されている、私たちの本性に適するであろう対象である。それが本性に適するものであるとき、その対象は〈善〉であり、この情動は〈愛〉の一つの種類である。例として、神に対して、ある国に対して、ある個人に対して、ある君主に対して、ある都市に対して。
7
欲望論
7.1
わたしたちの未来による〈善〉と〈悪〉の感受:〈欲望〉 (再掲)
・
〈欲望〉(ルネ・デカルト(1596-1650))
わたしたち自身の現在の状況が、「喜び」を感じさせるとき、未来においてもそれを保存しようと「欲望」されるとき、そこには、私たちの本性に適するであろう何かが存在する。それが本性に適するものであるとき、それは〈善〉である。(
善の保存の欲望)
わたしたち自身の現在の状況が、「悲しみ」を感じさせるとき、未来においてはそれを無くそうと「欲望」されるとき、そこには、私たちの本性を害するであろう何かが存在する。それが本性を害するものであるとき、それは〈悪〉である。(
悪の不在の欲望、改善の欲望)
わたしたち自身の予測される未来が、避けるべき未来として「欲望」されるとき、そこには私たちの本性を害するであろう何かが存在する。それが本性を害するものであるとき、それは〈悪〉である。(
悪の回避の欲望)
わたしたち自身のめざすべき未来が、新たな未来の獲得として「欲望」されるとき、このめざすべき未来には私たちの本性に適するであろう何かが存在する。それが本性に適するものであるとき、それは〈善〉である。(
善の獲得の欲望)
7.2
〈欲望〉の種類
・
〈欲望〉の種類は、〈愛〉や〈憎しみ〉の種類の数だけある。そして最も注目すべき最強の〈欲望〉は、〈快〉と〈嫌悪〉から生じる〈欲望〉である。(ルネ・デカルト(1596-1650))
7.3
〈安心〉〈希望〉〈不安〉〈執着〉〈絶望〉〈恐怖〉
・
善の獲得、悪の回避等が可能であると考えただけで、〈欲望〉がそそられる。そして、実現の見込みの大きさに応じて、次の情動が生じる:〈安心〉〈希望〉〈不安〉〈執着〉〈絶望〉。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・不安の過剰が〈恐怖〉の一種
8
自由意志論
・
認識の欠陥による不決定な状態は、程度の低い自由である。また、真と善を明晰に見たときの躊躇のない判断・選択は自由を減少させるものではない。悟性には到達し難い一層広い範囲にまで、意志は及び得る。これが自由意志であり、誤りと罪の原因でもある。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
悟性の及ぶ範囲を広げようとすることも、また、意志に違いない。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
意志の自由は、確かにある。これはまさに、完全に確実ではないことを信ずるのを拒み得る自由が、我々のうちにあることを経験したときに、自明かつ判然と示された。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
しかしながら、私が自分の意志により選択するように思えることも、これがこの全宇宙の一部であるのならば、この宇宙を支配する法則によって、あらかじめ予定されていたものに違いない。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
未解決問題:我々の精神が有限であるのに対して、この宇宙を支配する諸法則はあまりに深遠で知りがたく、いかにして人間の自由な行為が、未決定に残されるかを、未だ明快には理解することができていない。しかし、この自由は確かに経験される。(ルネ・デカルト(1596-1650))
9
徳
9.1 欲望は、真なる認識に従っているか
・
欲望の統御:欲望は、真なる認識に従っているか。また、私たちに依存しているものと、依存していないものが、よく区別できているか。(ルネ・デカルト(1596-1650))
9.2 私たちに依存しないもの
・
まったく私たちに依存しないものについては、それれがいかに善くても、情熱的に欲してはならない。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
私たちに依存しないものを可能だと認め欲望を感じるとき、これは偶然的運であり、知性の誤りから生じただけの幻なのである。なぜなら摂理は、運命あるいは不変の必然性のようなものであり、私たちは原因のすべてを知り尽くすことはできないからである。(ルネ・デカルト(1596-1650))
統制の錯覚:成功の原因を内的帰属し、失敗の原因は外的帰属する。また、完全に偶然的な出来事でも、何かしら原因と秩序と意味があり、予測と統制が可能であると考える。これらは、自己高揚的バイアスの一部であり、パーソナリティにとって潜在的に有益でもある。(ウォルター・ミシェル(1930-))

(出典:
COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK)
嫌悪的な課題や、ストレスや苦痛を伴う出来事を、予測可能で自分で統制できると信じると、そう信じることがたとえ現実と合わない幻想のような場合でさえ、否定的な感情が弱まり、課題遂行の悪化がかなり防げる。(ウォルター・ミシェル(1930-))
9.3 私たちにのみ依存するもの、自由意志
・
永遠の決定が、私たちの自由意志に依存させようとしたもの以外は、すべて必然的、運命的でないものは何も起こらない。私たちにのみ依存する部分に欲望を限定し、理性が認識できた最善を尽くすこと。(ルネ・デカルト(1596-1650))
永遠の決定が、私たちの自由意志に依存させようとしたもの以外は、すべて必然的、運命的でないものは何も起こらない。しかし、いずれを選ぶかに無関心であってはならないし、この神意の決定の不変の運命に頼ってもならない。私たちにのみ依存する部分を正確に見きわめ、この部分以上に欲望が広がらないようにすること。そして、理性が認識できた最善を尽くすこと。
9.4 意思決定に付随する情念:
〈不決断〉〈大胆〉〈勇気〉〈対抗心〉〈臆病〉〈恐怖〉
・
わたしたちに依存する行為の手段選択の困難から〈不決断〉、実現における困難さに対して、実現しようとする確固とした意志の強さに応じて、〈大胆〉〈勇気〉〈対抗心〉〈臆病〉〈恐怖〉の情念が生じる。(ルネ・デカルト(1596-1650))
不確かさへの志向:次のようなパーソナリティ次元が存在する。不確実さを正面から受けとめ新しい情報を求めて解決しようとする。逆に、不確実さに不快を感じて状況を回避し、新しい情報も求めない。(リチャード・M・ソレンティーノ(1943-)

(出典:
Western University )
検索(Richard M. Sorrentino)
・
不決断の効用、および過剰な不決断に対する治療法。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
臆病の効用、および臆病の治療法。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
恐怖の治療法。(ルネ・デカルト(1596-1650))
9.5 過去の意思決定に付随する情念:〈良心の悔恨〉
・
〈不決断〉が取り除かれないうちに何かの行動を決した場合、そこから〈良心の悔恨〉が生まれる。(ルネ・デカルト(1596-1650))
9.6 徳とは何か?
・
自由意志にのみ依存する善きことをなすのが、徳という欲望である。これは、私たちに依存するものであるゆえに、必ず成果をもたらす。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
人間は、自由意志により自分の行為の創造者となり、賞賛に値するその行為によって、人間における最高の完全性に至る。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
わたしたちが正当に賞賛または非難されうるのは、ただ、この自由意志に依拠する行動だけであり、これだけが、自分を重視する唯一の正しい理由である。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
徳とは、精神をある思考にしむける、精神のうちの習性である。この習性は、思考や教育から生み出される。(ルネ・デカルト(1596-1650))
9.7 徳に伴う情念、知的な〈喜び〉〈高邁〉、その反対の〈卑屈〉
9.7.1 様々な情念に伴う、知的な〈喜び〉
・
不思議な出来事を本で読んだり、舞台で演じられるのを見たりするときに感じるさまざまな情念は、私たちに、知的な喜びともいえる快感を経験させる。(ルネ・デカルト(1596-1650))
・
私たちが、自分が最善と判断したすべてを実行したことによる満足を、つねに持ってさえいれば、よそから来るいっさいの混乱は、精神を損なう力を少しももたない。むしろ精神は、みずからの完全性を認識させられ、その混乱は精神の喜びを増す。(ルネ・デカルト(1596-1650))
9.7.2 〈高邁〉
・
自ら最善と判断することを実行する確固とした決意と、この自由意志のみが真に自己に属しており、正当な賞賛・非難の理由であるとの認識が、自己を重視するようにさせる真の高邁の情念を感じさせる。(ルネ・デカルト(1596-1650))
自己効力期待:自分自身が行為の主体であり、自分にはうまく実行できるという期待と信念が、価値ある目標の追求、的確な判断、効果的な行動を助け、努力を持続させる。反対は無力感で、諦め、無気力、抑うつへの確実な道である。(ウォルター・ミシェル(1930-))

(出典:
COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK)
9.7.3 〈卑屈〉
・
自分は決断力がなく、自由意志の全面的な行使能力がないと考えるのが、卑屈すなわち悪しき謙虚であり、高邁の正反対である。(ルネ・デカルト(1596-1650))
9.8 〈高邁〉の情念をもつ人々の関係
・
高邁の情念をもつ人々は、善き意志という点で等しく、それ以外の美点で異なっていても過大に劣っているとか優れていると考えることはない。また、犯された過ちも認識の欠如によると考えて許そうとする。(ルネ・デカルト(1596-1650))
9.9 〈高邁〉とは異なる〈高慢〉
・
自由意志以外のすべての善、例えば才能、美、富、名誉などによって、自分自身を過分に評価してうぬぼれる人たちは、真の高邁をもたず、ただ高慢をもつだけだ。高慢は、つねにきわめて悪い。(ルネ・デカルト(1596-1650))
(出典:
wikipedia)

「その第一の部門は
形而上学で、認識の諸原理を含み、これには神の主なる属性、我々の心の非物質性、および我々のうちにある一切の明白にして単純な概念の解明が属します。第二の部門は
自然学で、そこでは物質的事物の真の諸原理を見出したのち、全般的には全宇宙がいかに構成されているかを、次いで個々にわたっては、この地球および最もふつうにその廻りに見出されるあらゆる物体、空気・水・火・磁体その他の鉱物の本性が、いかなるものであるかを調べます。これに続いて同じく個々について、
植物・動物の本性、とくに
人間の本性を調べることも必要で、これによって人間にとって有用な他の学問を、後になって見出すことが可能になります。かようにして、
哲学全体は一つの樹木のごときもので、その根は形而上学、幹は自然学、そしてこの幹から出ている枝は、他のあらゆる諸学なのですが、後者は結局三つの主要な学に帰着します。即ち医学、機械学および道徳、ただし私が言うのは、
他の諸学の完全な認識を前提とする窮極の知恵であるところの、最高かつ最完全な道徳のことです。ところで我々が果実を収穫するのは、木の根からでも幹からでもなく、枝の先からであるように、哲学の主なる効用も、我々が最後に至って始めて学び得るような部分の効用に依存します。」
(ルネ・デカルト(1596-1650)『哲学原理』仏訳者への著者の書簡、pp.23-24、[桂寿一・1964])
ルネ・デカルト(1596-1650)
デカルトの関連書籍(amazon)

検索(デカルト)

 「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
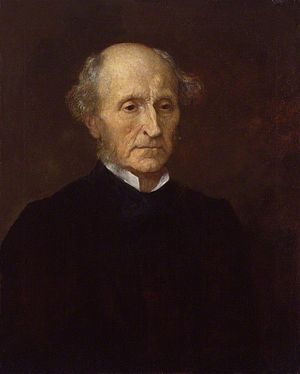 「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
 「私たちヒトは、多くの種類の苦しみ[受苦]に見舞われやすい[傷つきやすい]存在であり、私たちのほとんどがときに深刻な病に苦しんでいる。私たちがそうした苦しみにいかに対処しうるかに関して、それは私たち次第であるといえる部分はほんのわずかにすぎない。私たちがからだの病気やけが、栄養不良、精神の欠陥や変調、人間関係における攻撃やネグレクトなどに直面するとき、〔そうした受苦にもかかわらず〕私たちが生き続け、いわんや開花しうるのは、ほとんどの場合、他者たちのおかげである。そのような保護と支援を受けるために特定の他者たちに依存しなければならないことがもっとも明らかな時期は、幼年時代の初期と老年期である。しかし、これら人生の最初の段階と最後の段階の間にも、その長短はあれ、けがや病気やその他の障碍に見舞われる時期をもつのが私たちの生の特徴であり、私たちの中には、一生の間、障碍を負い続ける者もいる。」(中略)「道徳哲学の書物の中に、病気やけがの人々やそれ以外のしかたで能力を阻害されている〔障碍を負っている〕人々が登場することも《あるにはある》のだが、そういう場合のほとんどつねとして、彼らは、もっぱら道徳的行為者たちの善意の対象たりうる者として登場する。そして、そうした道徳的行為者たち自身はといえば、生まれてこのかたずっと理性的で、健康で、どんなトラブルにも見舞われたことがない存在であるかのごとく描かれている。それゆえ、私たちは障碍について考える場合、「障碍者〔能力を阻害されている人々〕」のことを「私たち」ではなく「彼ら」とみなすように促されるのであり、かつて自分たちがそうであったところの、そして、いまもそうであるかもしれず、おそらく将来そうなるであろうところの私たち自身ではなく、私たちとは区別されるところの、特別なクラスに属する人々とみなすよう促されるのである。」
「私たちヒトは、多くの種類の苦しみ[受苦]に見舞われやすい[傷つきやすい]存在であり、私たちのほとんどがときに深刻な病に苦しんでいる。私たちがそうした苦しみにいかに対処しうるかに関して、それは私たち次第であるといえる部分はほんのわずかにすぎない。私たちがからだの病気やけが、栄養不良、精神の欠陥や変調、人間関係における攻撃やネグレクトなどに直面するとき、〔そうした受苦にもかかわらず〕私たちが生き続け、いわんや開花しうるのは、ほとんどの場合、他者たちのおかげである。そのような保護と支援を受けるために特定の他者たちに依存しなければならないことがもっとも明らかな時期は、幼年時代の初期と老年期である。しかし、これら人生の最初の段階と最後の段階の間にも、その長短はあれ、けがや病気やその他の障碍に見舞われる時期をもつのが私たちの生の特徴であり、私たちの中には、一生の間、障碍を負い続ける者もいる。」(中略)「道徳哲学の書物の中に、病気やけがの人々やそれ以外のしかたで能力を阻害されている〔障碍を負っている〕人々が登場することも《あるにはある》のだが、そういう場合のほとんどつねとして、彼らは、もっぱら道徳的行為者たちの善意の対象たりうる者として登場する。そして、そうした道徳的行為者たち自身はといえば、生まれてこのかたずっと理性的で、健康で、どんなトラブルにも見舞われたことがない存在であるかのごとく描かれている。それゆえ、私たちは障碍について考える場合、「障碍者〔能力を阻害されている人々〕」のことを「私たち」ではなく「彼ら」とみなすように促されるのであり、かつて自分たちがそうであったところの、そして、いまもそうであるかもしれず、おそらく将来そうなるであろうところの私たち自身ではなく、私たちとは区別されるところの、特別なクラスに属する人々とみなすよう促されるのである。」








