共立的道徳と慣習的道徳
【ある規範的ルールが、成員の意見が一致しているが故に義務と考えられる「慣習的道徳」と、意見が一致せず仮に遵守されていなくとも義務と考えられる「共立的道徳」とが、区別できる。(ロナルド・ドゥオーキン(1931-2013))】道徳には、共立的道徳と慣習的道徳との区別ができる。裁判官が自ら遂行すべきであると考える義務の少なくともある部分は、慣習的道徳ではなく、むしろ共立的道徳に属すると考えられる。
(1)共立的道徳
(1.1)ある規範的ルールが成立している本質的要素として、その集団の成員の意見が一致していることを主張しないルール。
(1.2)人は嘘をつくべきでない義務に服すると考え、しかも他の多くの人々が嘘をついたとしても、この義務は相変わらず存在すると考えるのであれば、これは共立的道徳の一例となる。
(2)慣習的道徳
(2.1)その集団の成員の意見が一致していることを、本質的要素とするルール。
(2.2)ある社会的慣行が、もし実際に存在しなければこの義務も存在しないと考えれば、これは慣習的道徳の一例である。
「二種類の道徳はそれぞれ共立的(concurrent)道徳と慣習的(conventional)道徳と呼ぶことができるだろう。社会成員が同一あるいはほぼ同一の規範的ルールを主張することで一致しているが、彼らの意見が一致しているというこの事実を、ルールを主張する根拠の本質的要素とはみなしていない場合、社会は共立的道徳を提示するのに対し、一致の事実を、ルールを主張する根拠の本質的要素として挙げていれば、これは慣習的道徳を提示していることになる。もし教会に出かける人が、あらゆる人は教会で帽子を脱ぐ義務を有すると考えながらも、この種の社会的慣行が実際に存在しなければこの義務も存在しないと考えれば、これは慣習的道徳の一例である。また、人は嘘をつくべきでない義務に服すると彼らが考え、しかも他の多くの人々が嘘をついたとしてもこの義務は相変わらず存在すると考えるのであれば、これは共立的道徳の一例となるだろう。
したがって社会的ルール理論は、単に慣習的道徳の諸例に関してだけあてはまる理論となるように弱められねばならない。嘘言の場合に示されているような共立的道徳に関しても、ハートの言う実践的諸前提は充足されてはいるだろう。つまり人々は概して嘘をつくことはなく、このような態度を正当化するものとして、嘘言は悪であるという「ルール」を引用し、しかも嘘をつく者を非難するだろう。ハートの理論によれば、社会的ルールはこのような行為から構成されており、当該社会は嘘言を禁止する「ルールを有する」という社会学者の主張もこれにより正当化される。しかし嘘をつくべきでない義務を人々が主張した場合に彼らは上記のごとき社会的ルールを「援用している」と考えたり、彼らは社会的ルールの存在を自己の主張の必要条件とみなしている、と関することは彼らの主張の曲解である。むしろこれは共立的道徳の一例であり、したがって人々は社会的ルールを援用したり、これを自己の主張の必要条件と考えているわけではない。それ故社会的ルール理論は慣習的道徳に限定されねばならない。
理論がこのような仕方で更に弱められれば、司法的義務の問題に関する当該理論の意義も薄れてくる。裁判官が自ら遂行すべきであると考える義務の少なくともある部分は、慣習的道徳ではなくむしろ共立的道徳に属すると考えられよう。たとえば多くの裁判官は、民主的に選挙された立法府の決定を執行すべき義務に服すると考え、この義務を彼らが独立した価値をもつものとして受容する原理に基礎づけることもあるだろう。この場合彼らが当の原理を受容するのは、単に他の裁判官や公務担当者も同様にこの原理を受容しているからではない。しかし他方、これとは逆の想定をすることも少なくとも可能ではある。つまり典型的な法体系に属する少なくとも大半の裁判官は、一般的なある種の司法的慣行の存在を、自己の司法的義務上の要請を根拠づける本質的要因とみなしている、と考えることも可能だろう。」
(ロナルド・ドゥオーキン(1931-2013),『権利論』,第2章 ルールのモデルⅡ,1 社会的ルール,木鐸社(2003),pp.59-60,木下毅(訳),野坂泰司(訳),小林公(訳))
(索引:共立的道徳,慣習的道徳)
 |
(出典:wikipedia)
 「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。
「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。確かにこれらは我々が取り組まねばならぬ問題である。しかし問題の所在を指摘するだけでも、法実証主義が寄与したこと以上のものを我々に約束してくれる。法実証主義は、まさに自らの主張の故に、我々を困惑させ我々に様々な法理論の検討を促すこれら難解な事案を前にして立ち止まってしまうのである。これらの難解な事案を理解しようとするとき、実証主義者は自由裁量論へと我々を向かわせるのであるが、この理論は何の解決も与えず何も語ってはくれない。法を法準則の体系とみなす実証主義的な観方が我々の想像力に対し執拗な支配力を及ぼすのは、おそらくそのきわめて単純明快な性格によるのであろう。法準則のこのようなモデルから身を振り離すことができれば、我々は我々自身の法的実践の複雑で精緻な性格にもっと忠実なモデルを構築することができると思われる。」
(ロナルド・ドゥオーキン(1931-2013),『権利論』,第1章 ルールのモデルⅠ,6 承認のルール,木鐸社(2003),pp.45-46,木下毅(訳),野坂泰司(訳),小林公(訳))
ロナルド・ドゥオーキン(1931-2013)
ロナルド・ドゥオーキンの関連書籍(amazon)
検索(ドゥオーキン)
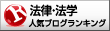
法律・法学ランキング
ブログサークル

 「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。








