発話という行為の構造
【発話という行為の構造:(A)発語行為(音声行為、用語行為、意味行為)、(B)発語内行為、(C・a)発語内行為と間接的に関連する発語媒介行為、(C・b)発語内行為とは関係のない発語媒介行為。(ジョン・L・オースティン(1911-1960))】(1)行為(A)発語行為
(1.1) 「何かを言う」とは、(a)物理的な音声を発する音声行為、(b)ある構文に従い単語を発する用語行為、(c)連続する複数の単語を使用し、ある言及対象と一定の意味を発する意味行為の、3つの側面から理解できる。(ジョン・L・オースティン(1911-1960))
(2)行為(B)発語内行為
(2.1) 適当な状況のもとにおいて、ある発言が、当の行為を実際に行なうことに他ならないような発言が存在する。妻と認めますか?「認めます」、「……と命名する」、「……を遺産として与える」、「……を賭ける」(ジョン・L・オースティン(1911-1960))
(2.2)(A1)ある一定の発言を含む慣習的な手続きの存在、(A2)発言者、状況の手続的適合性、(B1)手続きの適正な実行、(B2)完全な実行、(Γ1)発言者の考え、感情、参与者の意図の適合性、(Γ2)参与者の行為の適合性。(ジョン・L・オースティン(1911-1960))
(3)行為(C・a)発語内行為と間接的に関連する発語媒介行為
(3.1)何かを言うことは、通常の場合、聴き手、話し手、またはそれ以外の人物の感情、思考、行為に対して、結果としての何らかの効果を生ずることがある。
(3.2)上記のような効果を生ぜしめるという計画、意図、目的を伴って、発言を行うことも可能である。
(4)行為(C・b)発語内行為とは関係のない発語媒介行為
「発語内行為というこの概念をさらに研磨する作業に取りかかるのに先立って、発語行為、《および》発語内行為の両者を、さらに第三番目の種類に属する行為と比較してみることにしよう。
すなわち、発語行為を遂行し、それに伴って発語内行為を遂行するということがさらに、いま一つ別種の意味の行為を遂行することであるというような言葉の使用の第三の意味(C)が存在する。何かを言うことは、多くの場合というよりは、むしろ通常の場合、聴き手、話し手、またはそれ以外の人物の感情、思考、行為に対して結果としての効果を生ずることがある。さらに、その効果を生ぜしめるという計画(design)、意図(intention)、目的(purpose)を伴って発言を行うことも可能である。したがって、以上の点に留意するならば、話し手は目下の分類法における発語行為、もしくは発語内行為の遂行に対して、(C・a)間接的に(obliquely)のみ関連する、あるいは、(C・b)全然関連を持たないような、ある行為を遂行したのだと言うことができるであろう。この種の行為の遂行を《発語媒介的行為》(perlocutionary act, perlocution)の遂行と呼ぶ。しかし、当面はさしあたりこの概念について、これ以上の細心な定義を与えることは控え――もちろん、必要なことではあるが――単に例を掲げるにとどめておこう。
(例1)
行為(A)発語行為
彼は私に「彼女を射て」で射つことを意味し(mean)、「彼女」で彼女に言及していた。
行為(B)発語内行為
彼は私に、彼女を射つように促した。(あるいは助言した。命令した等々)
行為(C・a)すなわち、発語媒介行為
彼は私に対して、彼女を射つことを説得した。
行為(C・b)
彼は私に彼女を射たせた。
(例2)
行為(A)発語行為
彼は私に「君はそれをすることができない。」(You can't do that.)と言った。
行為(B)発語内行為
彼は、私がそれを行うことに抗議した。
行為(C・a)発語媒介行為
彼は私を制止した(pull up, check)。
行為(C・b)
彼は私を制止した。彼は私を正気に戻した等々。
彼は私を悩ませた。
さらに同様に、次のように区別することができるだろう。すなわち、「彼は………と言った」は発語行為であり、「彼は………と論じた」は発語内行為であり、また、「彼は、私に………と納得させた」は発語媒介行為である。」
(ジョン・L・オースティン(1911-1960),『いかにして言葉を用いて事を為すか』(日本語書籍名『言語と行為』),第8講 言語行為の一般理論Ⅱ,pp.174-176,大修館書店(1978),坂本百大(訳))
(索引:発語行為,発語内行為,発語媒介行為)
 |
(出典:wikipedia)
 「一般に、ものごとを精確に見出されるがままにしておくべき理由は、たしかに何もない。われわれは、ものごとの置かれた状況を少し整理したり、地図をあちこち修正したり、境界や区分をなかり別様に引いたりしたくなるかもしれない。しかしそれでも、次の諸点を常に肝に銘じておくことが賢明である。
「一般に、ものごとを精確に見出されるがままにしておくべき理由は、たしかに何もない。われわれは、ものごとの置かれた状況を少し整理したり、地図をあちこち修正したり、境界や区分をなかり別様に引いたりしたくなるかもしれない。しかしそれでも、次の諸点を常に肝に銘じておくことが賢明である。(a)われわれの日常のことばの厖大な、そしてほとんどの場合、比較的太古からの蓄積のうちに具現された区別は、少なくないし、常に非常に明瞭なわけでもなく、また、そのほとんどは決して単に恣意的なものではないこと、
(b)とにかく、われわれ自身の考えに基づいて修正の手を加えることに熱中する前に、われわれが扱わねばならないことは何であるのかを突きとめておくことが必要である、ということ、そして
(c)考察領域の何でもない片隅と思われるところで、ことばに修正の手を加えることは、常に隣接分野に予期せぬ影響を及ぼしがちであるということ、である。
実際、修正の手を加えることは、しばしば考えられているほど容易なことではないし、しばしば考えられているほど多くの場合に根拠のあることでも、必要なことでもないのであって、それが必要だと考えられるのは、多くの場合、単に、既にわれわれに与えられていることが、曲解されているからにすぎない。そして、ことばの日常的用法の(すべてではないとしても)いくつかを「重要でない」として簡単に片付ける哲学的習慣に、われわれは常にとりわけ気を付けていなければならない。この習慣は、事実の歪曲を実際上避け難いものにしてしまう。」
(ジョン・L・オースティン(1911-1960),『センスとセンシビリア』(日本語書籍名『知覚の言語』),Ⅶ 「本当の」の意味,pp.96-97,勁草書房(1984),丹治信春,守屋唱進)
ジョン・L・オースティン(1911-1960)
ジョン・L・オースティンの関連書籍(amazon)
検索(ジョン・L・オースティン)

 「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
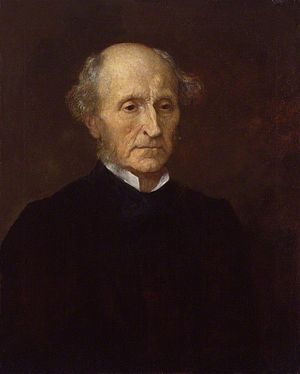 「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」


