在るべき法
【在るべき法の由来:(a)感情や態度などの主観的選好か、(b)命令として直感される諸原則か、(c)「普遍的な」意志の命令による目的か、(d)功利の原理か、(e)ある種の啓示によるか、(f)社会的ルールの存在。(ハーバート・ハート(1907-1992))】(1)在るべき法は、主観主義的、相対主義的、非認知的なものであるという考え。
自然を支配している諸法則を考えると、そこには善いものと悪いものを基礎づける何らかの根拠があるようには思えない。このことから、どうあるべきかという言明(価値の言明)は、何が起こっているのかという言明(事実の言明)からは基礎づけられ得ないと考えられた。
(1.1)ある哲学は、価値言明が感覚や感情や態度などの主観的選好の表現であると考えた。
(1.2)ある哲学は、価値言明というものは、ある個別具体的なケースが、行為の一般的な原則や方針の下に包摂されることを示すものであると考えた。そして、この一般的な原則や方針は、人間に対して何かしら一種の普遍的な命令として直感されるようなものとして理解された。
(1.3)ある哲学は、価値言明というものが、ある特定の目的を促進するものであると理解する。そして、私たちは、その目的のために何が適切な手段であるかを合理的に議論したり発見したりできる。しかし、目指される目的自体は、意志の命令あるいは感情や選好や態度の表現であるとされる。
(2)在るべき法には、何らかの普遍的な根拠があるという考え。
しかし、人間の感覚や感情、態度の主観的選好は何に由来するのか。何かしら命令的なものとして与えられる一般的な原則や方針は、何に由来するのか。目指されるものとして感知される目的は、何に由来するのか。
(2.1)道徳原則は、功利に関する実証可能な命題である。(ジェレミ・ベンサム(1748-1832))
(2.2)究極的な道徳原則は、啓示によって、またその指標としての功利を通して知ることができる。(ジョン・オースティン(1790-1859))
(3)規範的な言語で表現される価値言明は、ある集団において特定の社会的ルールが存在するか否かという事実問題である。この事実の存在は、人々の外的視点、内的視点の両面から判断される。
(3.1)注意すべきは、感情や態度などの主観的選好そのものが価値を基礎付けるわけではなく、事実としての社会的ルールの存在が、そのような感情や態度をしばしば生じさせるということである。
(3.2)また、社会的ルールの存在という事実にとって、ルールの常習的違反者が少数存在することは何ら矛盾したことではない。
参照: 特定の行動からの逸脱への批判や、基準への一致の要求を、理由のある正当なものとして受け容れる人々の習慣が存在するとき、この行動の基準が社会的ルールである。それは、規範的な言語で表現される。(ハーバート・ハート(1907-1992))
参照: 「外的視点」によって観察可能な行動の規則性、ルールからの逸脱に加えられる敵対的な反作用、非難、処罰が記録、理論化しても、「内的視点」を解明しない限り「法」の現象は真に理解できない。(ハーバート・ハート(1907-1992))
(4)在るべき法は、(3)の意味で、ある社会における社会的ルールの存在の事実の有無として客観的に論証可能なものであり、その社会の内においては相対主義的なものではない。ただし、異なる社会は、異なるルールを持ち得る。この意味では、相対的なものである。しかし、人類全体において認められる社会的ルールは、事実上、普遍的なものとなる。それでもなお、これら普遍的な諸ルールが、自然を支配している諸法則に、いかに由来しているのかと問うことができる。(未来のための哲学講座)
「「法実証主義」に対して強く抵抗している人びとに最も反感を持たせていると思われるものを、結論を述べるにあたって考察しないならば、片手落ちであろう。
在る法と在るべき法との区別の強調は、道徳的判断、道徳的区別、また、「価値」のまさに本質に関しての「主観主義的」「相対主義的」ないし「非認知的」な理論と呼ばれるものに基礎を置き、それを必要としている、と受け取られるかもしれない。
もちろん、功利主義者たち自身は、彼らの道徳哲学が私たちからみていかに不十分なものであるにせよ、(ケルゼンのような後の実証主義者とは異なり)そのような理論を支持していない。
オースティンは究極的な道徳原則は、啓示によってそして功利という「インデックス」を通して知ることのできる神の命令であると考えていたし、ベンサムは道徳原則を功利に関する実証可能な命題であると考えていた。
しかるに、私の考えるところでは(証明はできないのだが)、在る法と在るべき法との区別の主張は、「実証主義」という一般的題目の下で、ある道徳理論、すなわち、何が起こっているのかという言明(「事実の言明」)はどうあるべきかという言明(「価値言明」)とは根本的に異なるカテゴリーないしタイプに属するという道徳理論と混同された。
したがって、この混同の源を取り除いておく方がよいと思う。
このタイプの道徳理論は、現在さまざまなものが存在している。
ある理論によれば、在るべきこと、なされるべきことについての判断は、「感覚」や「感情」や「態度」の、また、「主観的選好」の表現であるか、または、それらを本質的要素として含んでいる。
別の理論によれば、そのような判断は、感覚や感情や態度の表現であるとともに他人にそれらを共有するように命令するものである。
また別の理論によれば、そのような判断は、行為の一般的な原則や方針の下に、ある個別具体的なケースが包摂されることを示すものである。
この原則や方針というのは、判断者が自ら「選択」し、「遵守すると決心」し、そして、それ自体何が起こっているかという認識ではなく、判断者自身も含めたすべての人へ向けられた一般的「定言命令」ないし命令とでもいうべきものである。
これら各説が共通して主張しているのは、なされるべきことについての判断は、「非認知的」要素を含んでいるので、事実の言明のように合理的な方法で議論、論証することはできず、また、事実の言明から導かれることを示すこともできず、なすべきことについての判断を事実の言明と結合したところから導かれるにすぎない、ということである。
このような理論に依拠するならば、たとえば、ある行為は悪いということを証明しようとすると、その行為は行為者が自己満足のためだけに故意に苦痛を加えるものであることを示すだけでは足らない。
そういう実証可能な「認知的」な事実の言明に、そのような状況の下での苦痛を加える行為は悪い、なすべきではないという原則、それ自体は実証可能でも「認知的」でもない一般的な原則を付け加えてはじめて、その行為が悪いということを示すことができる。
在るものと在るべきものとのこの一般的な区別に加えて、手段についての言明と道徳的目的についての言明との間でもそれに平行する厳格な区別がなされる。
私たちは、何かが与えられた目的にとって適切な手段であるかを、合理的に発見したり議論したりできるが、しかし、目的というものは、合理的に発見したり議論したりできるものではない。
それは、「意志の命令」であり、「感情」や「選好」や「態度」の表現であるとされる。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第1部 一般理論,2 実証主義と法・道徳分離論,pp.90-91,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),上山友一(訳),松浦好治(訳))
(索引:在るべき法)

(出典:wikipedia)
 「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
では要約に移りましょう。法学や哲学の将来に対する私の展望では、まだ終わっていない仕事がたくさんあります。私の国とあなたがたの国の両方で社会政策の実質的諸問題が個人の諸権利の観点から大いに議論されている時点で、われわれは、基本的人権およびそれらの人権と法を通して追求される他の諸価値との関係についての満足のゆく理論を依然として必要としているのです。したがってまた、もしも法理学において実証主義が最終的に葬られるべきであるとするならば、われわれは、すべての法体系にとって、ハード・ケースの解決の予備としての独自の正当化的諸原理群を含む、拡大された法の概念が、裁判官の任務の記述や遂行を曖昧にせず、それに照明を投ずるであろうということの論証を依然として必要としているのです。しかし現在進んでいる研究から判断すれば、われわれがこれらのものの少なくともあるものを手にするであろう見込みは十分あります。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第2部 アメリカ法理学,5 1776-1976年 哲学の透視図からみた法,pp.178-179,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),深田三徳(訳))
(索引:)
ハーバート・ハート(1907-1992)
ハーバート・ハートの関連書籍(amazon)
検索(ハーバート・ハート)


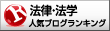
法律・法学ランキング
政治思想ランキング
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第1部 一般理論,2 実証主義と法・道徳分離論,pp.90-91,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),上山友一(訳),松浦好治(訳))
(索引:在るべき法)
 |
(出典:wikipedia)
 「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。では要約に移りましょう。法学や哲学の将来に対する私の展望では、まだ終わっていない仕事がたくさんあります。私の国とあなたがたの国の両方で社会政策の実質的諸問題が個人の諸権利の観点から大いに議論されている時点で、われわれは、基本的人権およびそれらの人権と法を通して追求される他の諸価値との関係についての満足のゆく理論を依然として必要としているのです。したがってまた、もしも法理学において実証主義が最終的に葬られるべきであるとするならば、われわれは、すべての法体系にとって、ハード・ケースの解決の予備としての独自の正当化的諸原理群を含む、拡大された法の概念が、裁判官の任務の記述や遂行を曖昧にせず、それに照明を投ずるであろうということの論証を依然として必要としているのです。しかし現在進んでいる研究から判断すれば、われわれがこれらのものの少なくともあるものを手にするであろう見込みは十分あります。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第2部 アメリカ法理学,5 1776-1976年 哲学の透視図からみた法,pp.178-179,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),深田三徳(訳))
(索引:)
ハーバート・ハート(1907-1992)
ハーバート・ハートの関連書籍(amazon)
検索(ハーバート・ハート)
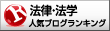
法律・法学ランキング

政治思想ランキング





