表現の意図
【ある表現が、意義のみを表現しているのか、意味の現存を前提としているのかは、表現の意図によって支えられている。(ゴットロープ・フレーゲ(1848-1925))】(1.3)追加記載。
(1)記号の意義と意味
記号、意義、意味の間の関係(ゴットロープ・フレーゲ(1848-1925))
(1.1)記号に対して一つの定まった意義が対応し、その意義に対してまた一つの定まった意味が対応する。
記号 → 一つの意義 → 一つの意味
=一つの対象
(1.2)例。
参照: 固有名の意義とは? 固有名の意味とは?(ゴットロープ・フレーゲ(1848-1925))
記号 → 記号の意義 → 記号の意味
あるいは
固有名
語
記号結合
表現
記号 → 記号によって → 記号によって
表現された 表示された
対象の様態 特定の対象
※「記号」は「意義」を「表現する」。
※「記号」は「意味」を「表示する」。
宵の明星 → 太陽が沈んだ後、→(金星)
西の空にどの星
よりも先に、一
番明るく輝いて
いる星。
明けの明星→ 太陽が昇る前に、→(金星)
東の空にどの星
よりも後まで、
一番明るく輝い
ている星。
金星 → 太陽系で、太陽 →(金星)
に近い方から二
番目の惑星。
(1.3)ある表現が、意義のみを表現しているのか、意味の現存を前提としているのかは、表現の意図によって支えられている。
(1.3.1)例えば「月は地球より小さい。」は、意義のみではなく、意味が前提されている。
(1.3.2)例えば、月の表象について語ることが意図されているならば、「私がもつ月の表象」という表現を使わなければならない。
(1.3.3)もちろん、前提された意図に対して、誤った表現がなされることもあり得るし、解釈者が意図を誤って解釈することもあり得よう。
「簡潔にして正確な表現を可能とするために以下のような用語法を確定しておきたい。すなわち固有名(語、記号、記号結合、表現)は、その意義を表現し(ausdrücken)、また、その意味を意味する(bedeuten)、または、その意味を表示する(bezeichnen)。我々は記号によって意義を表現し、記号によってその記号の意味を表示する。
観念論者や懐疑論者の側からは、このような見解に対しておそらくすでに以前から反論がなされていることだろう。「君は、月を対象として語ることに躊躇していないが、月という名がそもそも一つの意味をもつことを君は何を根拠に知ったのか。また、ともかくも何ものかが一つの意味をもつことは何から知ったのか」。このような反論に対して、私は、我々がもつ月の表象について語ることが我々の意図(Absicht)ではなく、また我々が「月」と言うときには、意義のみで満足せずに一つの意味を前提(voraussetzen)していると答えたい。「月は地球より小さい」という文において月の表象が話題になっているとすると、この文は意義を失う。話し手が月の表象を話題にしようとするためには、「私がもつ月の表象」という表現を使わなければならないであろう。ところで、我々が何ものかを前提するという際に誤りを犯すことはもちろん可能である。そして、そのような誤りが実際に生じたこともある。しかし、ここで、場合によると我々が常に誤りを犯しているのではないかという疑問に対しては答えないままでいることが許される。なぜならば、当面、記号の意味について語ることを正当化するためには、そのような意味の現存する場合という留保が必要であるにせよ、語りまたは思考において我々がもつ意図を指摘しておけば十分であるからである。」
(ゴットロープ・フレーゲ(1848-1925)『意味と意義について』31-32、フレーゲ著作集4、pp.77-78、土屋俊)
(索引:意義を表現する,意味を表示する,表現の意図,表現の前提)
 |
(出典:wikipedia)
 「1. 思考の本質を形づくる結合は、表象の連合とは本来異なる。
「1. 思考の本質を形づくる結合は、表象の連合とは本来異なる。2. 違いは、[思考の場合には]結合に対しその身分を裏書きする副思想(Nebengedanke)が存在する、ということだけにあるのではない。
3. 思考に際して結合されるものは、本来、表象ではなく、物、性質、概念、関係である。
4. 思想は、特殊な事例を越えてその向こう側へと手を伸ばす何かを常に含んでいる。そして、これによって、特殊な事例が一般的な何かに帰属するということに気づくのである。
5. 思想の特質は、言語では、繋辞や動詞の人称語尾に現われる。
6. ある結合[様式]が思想を形づくっているかどうかを識別するための基準は、その結合[様式]について、それは真であるかまたは偽であるかという問いが意味を持つか否かである。
7. 真であるものは、私は、定義不可能であると思う。
8. 思想を言語で表現したものが文である。我々はまた、転用された意味で、文の真理についても語る。
9. 文は、思想の表現であるときにのみ、真または偽である。
10.「レオ・ザクセ」が何かを指示するときに限り、文「レオ・ザクセは人間である」は思想の表現である。同様に、語「この机」が、空虚な語でなく、私にとって何か特定のものを指示するときに限り、文「この机はまるい」は思想の表現である。
11. ダーウィン的進化の結果、すべての人間が 2+2=5 であると主張するようになっても、「2+2=4」は依然として真である。あらゆる真理は永遠であり、それを[誰かが]考えるかどうかということや、それを考える者の心理的構成要素には左右されない。
12. 真と偽との間には違いがある、という確信があってはじめて論理学が可能になる。
13. 既に承認されている真理に立ち返るか、あるいは他の判断を利用しないかのいずれか[の方法]によって、我々は判断を正当化する。最初の場合[すなわち]、推論、のみが論理学の対象である。
14. 概念と判断に関する理論は、推論の理論に対する準備にすぎない。
15. 論理学の任務は、ある判断を他の判断によって正当化する際に用いる法則を打ち立てることである。ただし、これらの判断自身は真であるかどうかはどうでもよい。
16. 論理法則に従えば判断の真理が保証できるといえるのは、正当化のために我々が立ち返る判断が真である場合に限る。
17. 論理学の法則は心理学の研究によって正当化することはできない。
」 (ゴットロープ・フレーゲ(1848-1925)『論理学についての一七のキー・センテンス』フレーゲ著作集4、p.9、大辻正晴)
ゴットロープ・フレーゲ(1848-1925)
フレーゲの関連書籍(amazon)
検索(フレーゲ)
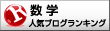
数学ランキング
ブログサークル

 「文句なしに、幸福な生は善であり、不幸な生は悪なのだ、という点に再三私は立ち返ってくる。そして《今》私が、《何故》私はほかでもなく幸福に生きるべきなのか、と自問するならば、この問は自ら同語反復的な問題提起だ、と思われるのである。即ち、幸福な生は、それが唯一の正しい生《である》ことを、自ら正当化する、と思われるのである。
「文句なしに、幸福な生は善であり、不幸な生は悪なのだ、という点に再三私は立ち返ってくる。そして《今》私が、《何故》私はほかでもなく幸福に生きるべきなのか、と自問するならば、この問は自ら同語反復的な問題提起だ、と思われるのである。即ち、幸福な生は、それが唯一の正しい生《である》ことを、自ら正当化する、と思われるのである。


 「もし社会的情動とその後の感情が存在しなかったら、たとえ他の知的能力は影響されないという非現実的な仮定を立てても、倫理的行動、宗教的信条、法、正義、政治組織といった文化的構築物は出現していなかったか、まったく別の種類の知的構築物になっていたかのいずれかだろう。が、少し付言しておきたい。私は情動と感情だけがそうした文化的構築物を出現させているなどと言おうとしているのではない。第一に、そうした文化的構築物の出現を可能にしていると思われる神経生物学的傾性には、情動と感情だけでなく、人間が複雑な自伝を構築するのを可能にしている大容量の個人的記憶、そして、感情と自己と外的事象の密接な相互関係を可能にしている延長意識のプロセスがある。第二に、倫理、宗教、法律、正義の誕生に対する単純な神経生物学的解釈にはほとんど望みがもてない。あえて言うなら、将来の解釈においては神経生物学が重要な役割を果たすだろう。しかし、こうした文化的現象を十分に理解するには、人間学、社会学、精神分析学、進化心理学などからの概念と、倫理、法律、宗教という分野における研究で得られた知見を考慮に入れる必要がある。実際、興味深い解釈を生み出す可能性がもっとも高いのは、これらすべての学問分野と神経生物学の〈双方〉から得られた統合的知識にもとづいて仮説を検証しようとする新しい種類の研究だ。」
「もし社会的情動とその後の感情が存在しなかったら、たとえ他の知的能力は影響されないという非現実的な仮定を立てても、倫理的行動、宗教的信条、法、正義、政治組織といった文化的構築物は出現していなかったか、まったく別の種類の知的構築物になっていたかのいずれかだろう。が、少し付言しておきたい。私は情動と感情だけがそうした文化的構築物を出現させているなどと言おうとしているのではない。第一に、そうした文化的構築物の出現を可能にしていると思われる神経生物学的傾性には、情動と感情だけでなく、人間が複雑な自伝を構築するのを可能にしている大容量の個人的記憶、そして、感情と自己と外的事象の密接な相互関係を可能にしている延長意識のプロセスがある。第二に、倫理、宗教、法律、正義の誕生に対する単純な神経生物学的解釈にはほとんど望みがもてない。あえて言うなら、将来の解釈においては神経生物学が重要な役割を果たすだろう。しかし、こうした文化的現象を十分に理解するには、人間学、社会学、精神分析学、進化心理学などからの概念と、倫理、法律、宗教という分野における研究で得られた知見を考慮に入れる必要がある。実際、興味深い解釈を生み出す可能性がもっとも高いのは、これらすべての学問分野と神経生物学の〈双方〉から得られた統合的知識にもとづいて仮説を検証しようとする新しい種類の研究だ。」

 「こうした結果によって、行為へと至る自発的プロセスにおける、意識を伴った意志と自由意志の役割について、従来とは異なった考え方が導き出されます。私たちが得た結果を他の自発的な行為に適用してよいなら、意識を伴った自由意志は、私たちの自由で自発的な行為を起動してはいないということになります。その代わり、意識を伴う自由意志は行為の成果や行為の実際のパフォーマンスを制御することができます。この意志によって行為を進行させたり、行為が起こらないように拒否することもできます。意志プロセスから実際に運動行為が生じるように発展させることもまた、意識を伴った意志の活発な働きである可能性があります。意識を伴った意志は、自発的なプロセスの進行を活性化し、行為を促します。このような場合においては、意識を伴った意志は受動的な観察者にはとどまらないのです。
「こうした結果によって、行為へと至る自発的プロセスにおける、意識を伴った意志と自由意志の役割について、従来とは異なった考え方が導き出されます。私たちが得た結果を他の自発的な行為に適用してよいなら、意識を伴った自由意志は、私たちの自由で自発的な行為を起動してはいないということになります。その代わり、意識を伴う自由意志は行為の成果や行為の実際のパフォーマンスを制御することができます。この意志によって行為を進行させたり、行為が起こらないように拒否することもできます。意志プロセスから実際に運動行為が生じるように発展させることもまた、意識を伴った意志の活発な働きである可能性があります。意識を伴った意志は、自発的なプロセスの進行を活性化し、行為を促します。このような場合においては、意識を伴った意志は受動的な観察者にはとどまらないのです。

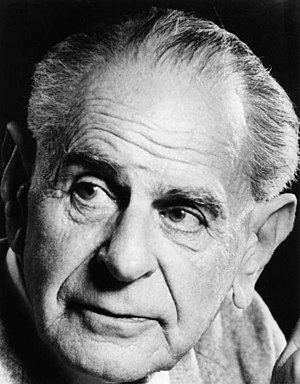 「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。
「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

 「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。
「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。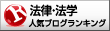

 「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。



