半影的問題における合理的決定
【半影的問題における合理的決定の解明には、(a)何らかの「べき」観点の必要性、(b)にもかかわらず、在る法と在るべき法の区別、(c)法の不完全性と中核部分の正しい理解、が必要である。(ハーバート・ハート(1907-1992))】
(1)半影的問題における司法的決定が合理的であるためには、下記のことが、ある適切に広い意味での「法」の一部分として考えられるかもしれない。
(1.1)「在るべきもの」の観点が含まれる。「べき」という言葉は、ある批判の基準の存在を反映している。
(1.2)批判の基準は、道徳的なものとは限らない。
(1.3)在るものと、さまざまな観点からの在るべきものとの間に、区別がなければならない。
(1.4)目標、社会的な政策や目的が含まれるかもしれない。
(2)しかし、在る法と在るべき法との功利主義的な区別は、必要である。
参照:
在るべき法についての基準が何であれ、在る法と在るべき法の区別を曖昧にすることは誤りである。(ジョン・オースティン(1790-1859))
参照:
在る法と在るべき法の区別は「しっかりと遵守し、自由に不同意を表明する」という処方の要である。(a)法秩序の権威の正しい理解か、悪法を無視するアナーキストか、(b)在る法の批判的分析か、批判を許さない反動家か。(ジェレミ・ベンサム(1748-1832))
(3)ルールの適用のはっきりしているケースと、半影的決定との間には本質的な連続性が存在する。すなわち、裁判官は、見付けられるべくそこに存在しており、正しく理解しさえすればその中に「隠れている」のがわかるルールを「引き出している」。
(4)(1)(2)(3)の要請を、すべて充たすことができるだろうか。この問題の解決のためには、以下の2つのことが重要だと思われる。
(4.1)法は、どうしようもなく、不完全なものだということ。
(4.2)法は、ある最も重要な意味において、確定した意味という中核部分を持つということ。不完全で曖昧であるにしても、まず線がなければならない。
「明らかに、もし形式主義の誤りを指摘することによって功利主義者の区別が誤りであると示そうとするならば、論旨を徹底的に言い直さなければならない。
司法的決定が合理的であるためには在るべきものの観点から決定が下されなければならないだけではなく、目標、すなわち、決定が合理的なものになるために裁判官が訴えかけるべき社会的な政策や目的は、それ自体、ある適切に広い意味での「法」の一部分として考えられ、こういう法の観念は功利主義者の使う観念よりも有益なものである、ということが論旨となるはずである。
このように論旨を言いかえると次のような主張に行きつく。すなわち、半影の問題が繰り返し現れるところで法的ルールが本質的に不完全なものであることがわかるというのではなく、
また、裁判官は、判断できないときには、立法をおこない、したがって、選択肢の中から創造的な選択をするというのではなく、
裁判官の選択の指針となる社会政策が、ある意味で、見付けられるべくそこに存在しており、裁判官は、正しく理解しさえすればその中に「隠れている」のがわかるルールを「引き出している」にすぎない、というのである。
これを司法的立法と呼ぶと、ルールの適用のはっきりしているケースと半影的決定との間にある本質的連続性が曖昧になってしまう。
このように論旨を語ることが有益であるか否かについては後で検討しようと考えるが、ここでは、言うまでもないことではあるが、もし指摘しておかなければ問題をもつれさせると危惧されるので、次のことを指摘しておきたい。
形式主義的、文言解釈主義的な方法で盲目的になされる決定の対極にあるのは在るべきものの観念を考慮して知性的になされる決定であるということから、法と道徳の接合する点が存在することになる、ということにはならない。
「べき」という言葉についてあまりに素朴に考えないように注意しなければならない。
在る法と在るべき法との間に区別がないからではない。その逆である。在るものと、さまざまな観点からの在るべきものとの間に、区別がなければならないからである。
「べき」という言葉は、ある批判の基準の存在を反映しているにすぎない。
これらの基準の一つは道徳的な基準であるが、しかし、すべての基準が道徳的であるわけではない。
隣人に向かって「嘘をつくべきではない」と言うときには、それはたしかに道徳的判断であろうが、しかし、毒を盛るのに失敗した者が「もう一服盛っておくべきだった」と言うこともある。
つまり、言いたいことは、機械的、形式的決定に対置される知性的決定は、必ずしも道徳的理由から擁護される決定と同一ではないということである。
「そうだ、それは正しい。それが在るべき姿だ」という表明が、ある承認された目的や政策がそれによって推進されたことだけを意味し、その政策や決定の道徳的性格の是認を意味しない場合も多く存在する。
したがって、機械的な決定と知性的な決定との対照は、最も有害な目的の追求に向けられた体系の中でも起こりうる。
この対照は、私たちの法的体系にみられるように、正義の原則と個人の道徳的要求とを広く受け入れている法的体系の中でのみ見られるものではない。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第1部 一般理論,2 実証主義と法・道徳分離論,pp.76-78,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),上山友一(訳),松浦好治(訳))
(索引:)
「半影の問題について知性的な決定とは、機械的になされるのではなく、道徳的原則と呼ばれるものに限られず、目標、目的、政策を考慮してなされるものである、ということがもし正しいとするならば、この重要な事実を表現するのに、在る法と在るべき法との功利主義的な区別を止めるべきだと主張するのは賢明なことであろうか。
おそらく、それが賢明だという主張を理論的に反駁することはできない。というのは、それは、結果的に、法的ルールについての私たちの観念を見直す《切っ掛け》だからである。
それによって私たちは「ルール」の中にさまざまの目標や政策を含めるように誘われる。
これらの目標や政策は、その重要性からして、法的ルールの意味が確定している中核部分と同様に法と呼ばれてしかるべきであり、これらの目標や政策を考慮してルールの半影的なケースには決定が下されるべきではないか。
この誘いを論駁することはできないが、しかし、断ることはできよう。
この誘いを断る理由として私は二つの理由をあげたい。第一に、司法過程について学んだことはすべては、より神秘的でない他の形で表現できる。
法はどうしようもなく不完全であるから、半影的ケースについては社会的目標を考慮して合理的に決定しなければならない、ということができる。
ホームズなら、「一般的命題は具体的ケースを決定しない」という事実を鮮明に察知していたのであるから、このような形で表現するだろうと私は考える。
第二に、功利主義的な区別を主張することは、ある最も重要な意味において、確定した意味という中核部分は法であること、そして、曖昧であるにしても、まず線がなければならないことを強調するものである。
もしそうでなければ、裁判所の判決を制御しているルールという観念は、「リアリスト」の幾人かが――その最も極端な風潮の中で、私が思うに、不適切な根拠に基づいて――主張したように、無意味なものになってしまうだろう。
逆に、この区別を緩めようとすること、すなわち、在る法と在るべき法との間に両者が融合して一体となった部分があるという不可解な主張をすることは、すべての法的問題は基本的に半影の問題のようなものであると示唆するものである。
ルールの持つ中心的意味の中には法の中心的要素は発見できない、また、社会政策の観点から問題《すべて》を再検討することと法的ルールの本質との間には矛盾するところはない、と主張するものである。
もちろん、半影に注目することは結構なことである。半影の問題はロー・スクールにおいてはまさに日々の糧である。しかし、半影に注目することとそれに夢中になることとは違う。
半影に夢中になるのは、言ってみれば、アメリカの法的伝統における混乱の温床であり、それはイギリスの法的伝統における形式主義に対応する。
もちろん、ルールは権威を持つという考え方を放棄することもできる。
この事件はルールそして先例の範囲に明らかに包摂されるものだという議論を支持するのをやめたり、また、それに意味すら認めないこともできる。そのような推論をすべて「自動的」「機械的」と呼ぶこともできる。これは裁判所批判の常套手段である。
しかし、これが私たちの望むものに《他ならない》と確信するまでは、功利主義的な区別を抹消することによってこれを助長するべきではない。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第1部 一般理論,2 実証主義と法・道徳分離論,pp.79-80,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),上山友一(訳),松浦好治(訳))
(索引:半影的問題)

(出典:
wikipedia)

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
では要約に移りましょう。法学や哲学の将来に対する私の展望では、まだ終わっていない仕事がたくさんあります。私の国とあなたがたの国の両方で社会政策の実質的諸問題が個人の諸権利の観点から大いに議論されている時点で、われわれは、基本的人権およびそれらの人権と法を通して追求される他の諸価値との関係についての満足のゆく理論を依然として必要としているのです。したがってまた、もしも法理学において実証主義が最終的に葬られるべきであるとするならば、われわれは、すべての法体系にとって、ハード・ケースの解決の予備としての独自の正当化的諸原理群を含む、拡大された法の概念が、裁判官の任務の記述や遂行を曖昧にせず、それに照明を投ずるであろうということの論証を依然として必要としているのです。しかし現在進んでいる研究から判断すれば、われわれがこれらのものの少なくともあるものを手にするであろう見込みは十分あります。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第2部 アメリカ法理学,5 1776-1976年 哲学の透視図からみた法,pp.178-179,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),深田三徳(訳))
(索引:)
ハーバート・ハート(1907-1992)
ハーバート・ハートの関連書籍(amazon)

検索(ハーバート・ハート)


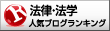 法律・法学ランキング
法律・法学ランキング
 政治思想ランキング
政治思想ランキング

 「一般に、ものごとを精確に見出されるがままにしておくべき理由は、たしかに何もない。われわれは、ものごとの置かれた状況を少し整理したり、地図をあちこち修正したり、境界や区分をなかり別様に引いたりしたくなるかもしれない。しかしそれでも、次の諸点を常に肝に銘じておくことが賢明である。(a)われわれの日常のことばの厖大な、そしてほとんどの場合、比較的太古からの蓄積のうちに具現された区別は、少なくないし、常に非常に明瞭なわけでもなく、また、そのほとんどは決して単に恣意的なものではないこと、(b)とにかく、われわれ自身の考えに基づいて修正の手を加えることに熱中する前に、われわれが扱わねばならないことは何であるのかを突きとめておくことが必要である、ということ、そして(c)考察領域の何でもない片隅と思われるところで、ことばに修正の手を加えることは、常に隣接分野に予期せぬ影響を及ぼしがちであるということ、である。実際、修正の手を加えることは、しばしば考えられているほど容易なことではないし、しばしば考えられているほど多くの場合に根拠のあることでも、必要なことでもないのであって、それが必要だと考えられるのは、多くの場合、単に、既にわれわれに与えられていることが、曲解されているからにすぎない。そして、ことばの日常的用法の(すべてではないとしても)いくつかを「重要でない」として簡単に片付ける哲学的習慣に、われわれは常にとりわけ気を付けていなければならない。この習慣は、事実の歪曲を実際上避け難いものにしてしまう。」
「一般に、ものごとを精確に見出されるがままにしておくべき理由は、たしかに何もない。われわれは、ものごとの置かれた状況を少し整理したり、地図をあちこち修正したり、境界や区分をなかり別様に引いたりしたくなるかもしれない。しかしそれでも、次の諸点を常に肝に銘じておくことが賢明である。(a)われわれの日常のことばの厖大な、そしてほとんどの場合、比較的太古からの蓄積のうちに具現された区別は、少なくないし、常に非常に明瞭なわけでもなく、また、そのほとんどは決して単に恣意的なものではないこと、(b)とにかく、われわれ自身の考えに基づいて修正の手を加えることに熱中する前に、われわれが扱わねばならないことは何であるのかを突きとめておくことが必要である、ということ、そして(c)考察領域の何でもない片隅と思われるところで、ことばに修正の手を加えることは、常に隣接分野に予期せぬ影響を及ぼしがちであるということ、である。実際、修正の手を加えることは、しばしば考えられているほど容易なことではないし、しばしば考えられているほど多くの場合に根拠のあることでも、必要なことでもないのであって、それが必要だと考えられるのは、多くの場合、単に、既にわれわれに与えられていることが、曲解されているからにすぎない。そして、ことばの日常的用法の(すべてではないとしても)いくつかを「重要でない」として簡単に片付ける哲学的習慣に、われわれは常にとりわけ気を付けていなければならない。この習慣は、事実の歪曲を実際上避け難いものにしてしまう。」

 「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。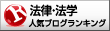

 「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。
「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。





