向社会的処罰者
【互いの協力によって成立している集団における「ただ乗り者」に対して、人は怒りの感情を持ち、代価を支払っても処罰しようとする。このような、人間が持つ向社会的処罰の傾向は、集団内の互いの協力を高める。(エルンスト・フェール(1956-))】「公共財ゲーム」という実験での検証結果である。
(1)「ただ乗り者」を罰する機会がない場合
(1.1)最初は、ほとんどの人が協力的である。
(1.2)次第に、ただ乗り者が現れる。
(1.3)協力的な参加者は、自分がカモになっていることを知ると、次第に協力しなくなっていく。
(1.4)最後には、協力する者がほとんどいなくなる。
(2)「ただ乗り者」を罰する機会がある場合
(2.1)ただ乗り者を罰するには、自ら代価を支払わなければならないにもかかわらず、処罰者が現れる。
(2.2)そして、全体の協力の度合が高くなる。
(2.3)また、ゲームに罰が取り入れられると、実際に誰かが罰を下す前に、協力が高まる。すなわち、自身には何の得もないにもかかわらず処罰者が現れるという予想を、参加者は持っている。
(3)人は、向社会的処罰者である。
(3.1)互いの協力によって成立している集団において、自らは協力しないで利益を得る「ただ乗り者」に対して、人は怒りの感情を持つ。
(3.2)怒りは、自分には何の得もなく、むしろ代価を支払わなければならない状況においても、「ただ乗り者」を処罰するという行動へと、人を動機づける。
(3.3)処罰するという行動の可能性は、集団内での協力を高める。
(3.4)集団内の協力が高まることで、他の集団を打ち負かすのを助けることになる。
(出典:wikipedia)

エルンスト・フェール(1956-)
検索(Ernst Fehr)
「研究室で行なわれた多数の実験により、人が実際に向社会的処罰者であることが確認されている。こうした実験でもっとも有名なのが、エルンスト・フェールとシモン・ゲヒターがいわゆる「公共財ゲーム」を使って行なった実験だ。これは、「コモンズの悲劇」とよく似た多人数版の「囚人のジレンマ」だ。参加者は全員、ゲームの冒頭で決まった額のお金を受け取り、いくつかのグループに分けられる。参加者は一ラウンドごとに共同資金として一定金額を出資する。共同資金に預けられたお金は実験者によって何倍かに増やされてから、参加者に均等に分配される。誰がいくら出資するかはわからないようになっている。
この場合、集団としての合理的行動は、参加者全員が所持金を全額共同資金に出資するというものだ。そうすれば、実験者によって増やされるお金の総額が最大になり、集団全体の取り分も最大化される。」(中略)「ところが、個人としての合理的行動は(利己主義者だったら)、まったく出資しない――つまり、他の参加者の出資金に「ただ乗り」するというものだ。ただ乗り者は、最初に受け取ったお金をまるまる手元に残し、なおかつ共同資金の分け前にもあずかれる。この場合、ただ乗り者がひとりで三人が協力的であれば、ただ乗り者は25ドルの純益を得るが、残りの人は各自たった5ドルの純益しか得られない。公共財ゲームのただ乗り者は、「囚人のジレンマ」での裏切りや、「コモンズの悲劇」で羊を「好きなだけ増やす」行為と似ている。
公共財ゲームをくり返すと次のようなパターンが見られる。ほとんどの人が最初は協力的で、少なくとも所持金の一部を共同資金に出資する。しかししだいに、ただ乗りをする人が現れる。共同資金への出資額を減らしたり、お金をまったく出さなくなったりするのだ。協力的な参加者は、自分がカモになっていることを知ると、出資額を減らしたり、出資をやめたりする。ラウンドを重ねるごとに出資額が減り、「うんざりだ」という参加者が増え、出資金はかぎりなくゼロに近づく。悲劇だ。」
「ところが、協力的参加者にただ乗り者を罰する機会を与えると、状況が変化する場合が多い。この場合の罰は「代価を伴う罰」で、誰かの取り分を減らすためにいくらか支払わなくてはならない。たとえば、次のラウンドで、ひとりが1ドル支払うと、ただ乗り者の取り分が4ドル減る。これは経済的に誰かの頭をゴツンと殴ることに相当する。実験者が、ただ乗り者を罰する機会を与えると、通常、共同資金の額は増える。重要な点は、処罰者が罰から何も得るものがなく、全員がそれを承知していても、この現象が起きることだ。それだけではない。ゲームに罰が取り入れられると、即座に、誰かが実際に罰を下す前に、協力が高まる。つまり、ただ乗りしようと考えている人が、ただ乗りすると、自分を罰したところで(物質的に)何の得もない人々にまで罰せられると予測するわけだ。
《なぜ》私たちは向社会的処罰者なのか? これについてはさかんに議論されている。ある人たちは、向社会的処罰は、直接互恵と評判管理に向って人類が進化させた性向のたんなる副産物だという。私たちは、協力しあう未来が築けそうにない相手を罰する。それは私たちの脳が、すべての人は協力のパートナーであり、誰かがつねに見張っているかもしれないと自動的に思い込んでいるからだ。小規模な狩猟採集集団で暮らすぶんには、不合理な思い込みではない。またある人たちは、向社会的処罰は、生物学的選択や文化選択を通して集団レベルで進化したという。向社会的処罰は集団にとってよいものであり、向社会的に処罰を与えることで、その人は、自分の集団が他の集団を打ち負かすのを助けているというのだ。これはたいへん興味深い議論ではあるが、自分の立場をはっきりさせる必要はない。本書の目的にとって重要なのは、向社会的処罰が生じるということと、それが現在よく知られている心の特徴に合致するということだ。
予測されるように、向社会的処罰は情動によって引き起こされる。フェールとゲヒターは参加者に、ただ乗りをした人にもし実験室の外で会うことがあったら、その人についてどう感じると思うかを尋ねた。ほとんどの人は、怒りを感じると思うと言い、立場が逆だったら怒りは《自分たちに》向けられるだろうと言った。このあきらかに道徳的な怒りを《義憤》と呼ぼう。」
(ジョシュア・グリーン(19xx-),『モラル・トライブズ』,第1部 道徳の問題,第2章 道徳マシン,岩波書店(2015),(上),pp.76-78,竹田円(訳))
(索引:向社会的処罰者)
 |
(出典:Joshua Greene)
 「あなたが宇宙を任されていて、知性と感覚を備えたあらたな種を創造しようと決意したとする。この種はこれから、地球のように資源が乏しい世界で暮らす。そこは、資源を「持てる者」に分配するのではなく「持たざる者」へ分配することによって、より多くの苦しみが取り除かれ、より多くの幸福が生み出される世界だ。あなたはあらたな生物の心の設計にとりかかる。そして、その生物が互いをどう扱うかを選択する。あなたはあらたな種の選択肢を次の三つに絞った。
「あなたが宇宙を任されていて、知性と感覚を備えたあらたな種を創造しようと決意したとする。この種はこれから、地球のように資源が乏しい世界で暮らす。そこは、資源を「持てる者」に分配するのではなく「持たざる者」へ分配することによって、より多くの苦しみが取り除かれ、より多くの幸福が生み出される世界だ。あなたはあらたな生物の心の設計にとりかかる。そして、その生物が互いをどう扱うかを選択する。あなたはあらたな種の選択肢を次の三つに絞った。種1 ホモ・セルフィッシュス
この生物は互いをまったく思いやらない。自分ができるだけ幸福になるためには何でもするが、他者の幸福には関心がない。ホモ・セルフィッシュスの世界はかなり悲惨で、誰も他者を信用しないし、みんなが乏しい資源をめぐってつねに争っている。
種2 ホモ・ジャストライクアス
この種の成員はかなり利己的ではあるが、比較的少数の特定の個体を深く気づかい、そこまでではないものの、特定の集団に属する個体も思いやる。他の条件がすべて等しければ、他者が不幸であるよりは幸福であることを好む。しかし、彼らはほとんどの場合、見ず知らずの他者のために、とくに他集団に属する他者のためには、ほとんど何もしようとはしない。愛情深い種ではあるが、彼らの愛情はとても限定的だ。多くの成員は非常に幸福だが、種全体としては、本来可能であるよりはるかに幸福ではない。それというのも、ホモ・ジャストライクアスは、資源を、自分自身と、身近な仲間のためにできるだけ溜め込む傾向があるからだ。そのためい、ホモ・ジャストライクアスの多くの成員(半数を少し下回るくらい)が、幸福になるために必要な資源を手に入れられないでいる。
種3 ホモ・ユーティリトゥス
この種の成員は、すべての成員の幸福を等しく尊重する。この種はこれ以上ありえないほど幸福だ。それは互いを最大限に思いやっているからだ。この種は、普遍的な愛の精神に満たされている。すなわち、ホモ・ユーティリトゥスの成員たちは、ホモ・ジャストライクアスの成員たちが自分たちの家族や親しい友人を大切にするときと同じ愛情をもって、互いを大切にしている。その結果、彼らはこの上なく幸福である。
私が宇宙を任されたならば、普遍的な愛に満たされている幸福度の高い種、ホモ・ユーティリトゥスを選ぶだろう。」(中略)「私が言いたいのはこういうことだ。生身の人間に対して、より大きな善のために、その人が大切にしているものをほぼすべて脇に置くことを期待するのは合理的ではない。私自身、遠くでお腹をすかせている子供たちのために使った方がよいお金を、自分の子供たちのために使っている。そして、改めるつもりもない。だって、私はただの人間なのだから! しかし、私は、自分が偽善者だと自覚している人間でありたい、そして偽善者の度合いを減らそうとする人間でありたい。自分の種に固有の道徳的限界を理想的な価値観だと勘違いしている人であるよりも。」
(ジョシュア・グリーン(19xx-),『モラル・トライブズ』,第4部 道徳の断罪,第10章 正義と公正,岩波書店(2015),(下),pp.357-358,竹田円(訳))
(索引:)
ジョシュア・グリーン(19xx-)
ジョシュア・グリーンの関連書籍(amazon)
検索(joshua greene)
検索(ジョシュア・グリーン)

心理学ランキング
ブログサークル

 「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。
「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。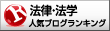


 「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。







