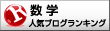裁判のルール
【個々の場合に第1次的ルールが破られたかどうかを、権威的に決定する司法的権能を、特定の個人に与えるという第2次的ルールが、裁判のルールである。他の公機関による刑罰の適用を命じる排他的権能も含まれる。(ハーバート・ハート(1907-1992))】(2.3)ルールの非効率性
(2.3.1)ルールが侵害されたかどうかの争いはいつも起こり、絶え間なく続く。法の歴史によれば、ルール違反の事実を権威的に決定する公機関の欠如は、最も重大な欠陥であり、他の欠陥より早く矯正される。
(2.3.2)ルール違反に対する処罰が、影響を受けた関係人達や集団一般に放置されている。
(2.3.3)違反者を捕え罰する、集団の非組織的な作用に費やされる時間が浪費される。
(2.3.4)自力救済から起こる、くすぶりつづける復讐の連鎖が続く。
(2.3.5)補われる第2次的ルール:裁判のルール
個々の場合に第1次的ルールが破られたかどうかを、権威的に決定する司法的権能を、特定の個人に与えるというルールを、人々が受け入れている。また、違反の事実を確認した場合、他の公機関による刑罰の適用を命じる排他的権能も含む。
(a)裁判官、裁判所、管轄権、判決といった概念を定めている。
(b)裁判のルールが存在するときは、裁判所の決定は何がルールであるかについての権威的な決定であるので、承認のルールにもなっている。
(c)社会的圧力の集中化、すなわち、私人による物理的処罰や暴力による自力救済の行為を部分的に禁じるとともに、刑罰の適用を命じる排他的権能を定める。
「第1次的ルールの単純な体制に対する第三の補完は、個々の場合に第1次的ルールが破られたかどうかを権威的に決定する権能を個人に与える第2次的ルールからなっているのであって、それは社会的圧力が散漫なため生じるルールの《非効率性》を矯正しようとするものである。
裁判の最小限の形態はそのような決定のなかにあり、われわれはそのような決定をする権能を与える第2次的ルールを「裁判のルール」rules of adjudication と呼ぶことにする。
このようなルールは、誰が裁判できるかを確認する一方、どういう手続に従うべきかを定めるだろう。
他の第2次的ルールと同じように、このルールも第1次的ルールと異なった平面にある。
このルールは裁判官に裁判する義務を課すほかのルールによって強化されるかもしれないが、裁判のルールは義務を課すのではなく司法的権能を与えるのであり、責務の違反についての司法的宣言に特別な地位を与えるのである。
またこのルールはほかの第2次的ルールと同様に一群の重要な法的概念を定めているのであり、この場合には裁判官、裁判所、管轄権、判決といった概念を定めている。
裁判のルールはこのように他の第2次的ルールと類似しているだけでなく、さらに密接な関連をもっている。
事実、裁判のルールがある体系は、必然的にまた原初的で不完全な種類のルールにもかかわっているのである。この理由は、もし裁判所がルールが破られたという事実について権威的な決定をなす権能を与えられているならば、この決定は何がルールであるかについての権威的な決定とみなされざるをえないからである。
したがって、裁判管轄権を与えているルールは、裁判所の決定によって第1次的ルールを確認する承認のルールにもなるだろうし、こういった判決は法の「法源」となるだろう。
裁判管轄権の最小形態と一緒になったこの承認のルールの形態は、たしかに非常に不完全だろう。権威的な原典や法令集と違って、判決は一般的な用語ではあらわされないだろうし、判決をルールへの権威的な指針として用いることは個々の決定からのいくぶん不確実な推論に頼るということであり、そしてその信頼度は解釈者の技術と裁判官の一貫性とに左右されざるをえないのである。
ほとんどの法体系では司法権能が第1次的ルールの違反の事実についての権威的決定に限られないことは言うまでもない。
たいていの体系は、しばらくして社会的圧力の集中化を進めることが有利であると知り、そこで私人による物理的処罰や暴力による自力救済の行為を部分的に禁じたのである。
その代わりに、それらの体系は違反に対する刑罰を指定するか少なくとも限定しているより進んだ第2次的ルールで責務の第1次的ルールを補っており、そして裁判官が違反の事実を確認した場合、他の公機関による刑罰の適用を命じる排他的権能を裁判官に与えたのである。これらの第2次的ルールが体系の集中化された公的「制裁」sanctions を提供するのである。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法の概念』,第5章 第1次的ルールと第2次的ルールの結合としての法,第3節 法の諸要素,pp.106-107,みすず書房(1976),矢崎光圀(監訳),石井幸三(訳))
(索引:裁判のルール)
 |
(出典:wikipedia)
 「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。では要約に移りましょう。法学や哲学の将来に対する私の展望では、まだ終わっていない仕事がたくさんあります。私の国とあなたがたの国の両方で社会政策の実質的諸問題が個人の諸権利の観点から大いに議論されている時点で、われわれは、基本的人権およびそれらの人権と法を通して追求される他の諸価値との関係についての満足のゆく理論を依然として必要としているのです。したがってまた、もしも法理学において実証主義が最終的に葬られるべきであるとするならば、われわれは、すべての法体系にとって、ハード・ケースの解決の予備としての独自の正当化的諸原理群を含む、拡大された法の概念が、裁判官の任務の記述や遂行を曖昧にせず、それに照明を投ずるであろうということの論証を依然として必要としているのです。しかし現在進んでいる研究から判断すれば、われわれがこれらのものの少なくともあるものを手にするであろう見込みは十分あります。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第2部 アメリカ法理学,5 1776-1976年 哲学の透視図からみた法,pp.178-179,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),深田三徳(訳))
(索引:)
ハーバート・ハート(1907-1992)
ハーバート・ハートの関連書籍(amazon)
検索(ハーバート・ハート)
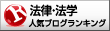
法律・法学ランキング

政治思想ランキング

 「国家が経済を規制しているのか、それとも経済が国家に権限をさずけているのかということは、この両者の実体が変えられぬかぎりは、重要な問題ではない。国家の各種の組織がより自由に、そして経済のそれらがより公正になるかどうかということが重要なのだ。しかしこのことも、ここで問われている真実なる生命という問題にとっては重要ではない。諸組織は、それら自体からしては自由にも公正にもなり得ないのである。決定的なことは、精神が、《汝》を言う精神、応答する精神が生きつづけ現実として存在しつづけるかどうかということ、人間の社会生活のなかに撒入されている精神的要素が、これからもずっと国家や経済に隷属させられたままであるか、それとも独立的に作用するようになるかどうかということであり、人間の個人生活のうちになおも持ちこたえられている精神的要素が、ふたたび社会生活に血肉的に融合するかどうかということなのである。社会生活がたがいに無縁な諸領域に分割され、《精神生活》もまたその領域のうちのひとつになってしまうならば、社会への精神の関与はむろんおこなわれないであろう。これはすなわち、《それ》の世界のなかに落ちこんでしまった諸領域が、《それ》の専制に決定的にゆだねられ、精神からすっかり現実性が排除されるということしか意味しないであろう。なぜなら、精神が独立的に生のなかへとはたらきかけるのは決して精神それ自体としてではなく、世界との関わりにおいて、つまり、《それ》の世界のなかへ浸透していって《それ》の世界を変化させる力によってだからである。精神は自己のまえに開かれている世界にむかって歩みより、世界に自己をささげ、世界を、また世界との関わりにおいて自己を救うことができるときにこそ、真に《自己のもとに》あるのだ。その救済は、こんにち精神に取りかわっている散漫な、脆弱な、変質し、矛盾をはらんだ理知によっていったいはたされ得ようか。いや、そのためにはこのような理知は先ず、精神の本質を、《汝を言う能力》を、ふたたび取り戻さねばならないであろう。」
「国家が経済を規制しているのか、それとも経済が国家に権限をさずけているのかということは、この両者の実体が変えられぬかぎりは、重要な問題ではない。国家の各種の組織がより自由に、そして経済のそれらがより公正になるかどうかということが重要なのだ。しかしこのことも、ここで問われている真実なる生命という問題にとっては重要ではない。諸組織は、それら自体からしては自由にも公正にもなり得ないのである。決定的なことは、精神が、《汝》を言う精神、応答する精神が生きつづけ現実として存在しつづけるかどうかということ、人間の社会生活のなかに撒入されている精神的要素が、これからもずっと国家や経済に隷属させられたままであるか、それとも独立的に作用するようになるかどうかということであり、人間の個人生活のうちになおも持ちこたえられている精神的要素が、ふたたび社会生活に血肉的に融合するかどうかということなのである。社会生活がたがいに無縁な諸領域に分割され、《精神生活》もまたその領域のうちのひとつになってしまうならば、社会への精神の関与はむろんおこなわれないであろう。これはすなわち、《それ》の世界のなかに落ちこんでしまった諸領域が、《それ》の専制に決定的にゆだねられ、精神からすっかり現実性が排除されるということしか意味しないであろう。なぜなら、精神が独立的に生のなかへとはたらきかけるのは決して精神それ自体としてではなく、世界との関わりにおいて、つまり、《それ》の世界のなかへ浸透していって《それ》の世界を変化させる力によってだからである。精神は自己のまえに開かれている世界にむかって歩みより、世界に自己をささげ、世界を、また世界との関わりにおいて自己を救うことができるときにこそ、真に《自己のもとに》あるのだ。その救済は、こんにち精神に取りかわっている散漫な、脆弱な、変質し、矛盾をはらんだ理知によっていったいはたされ得ようか。いや、そのためにはこのような理知は先ず、精神の本質を、《汝を言う能力》を、ふたたび取り戻さねばならないであろう。」

 「精神も徳も、これまでに百重にもみずからの力を試み、道に迷った。そうだ、人間は一つの試みであった。ああ、多くの無知と迷いが、われわれの身において身体と化しているのだ!
「精神も徳も、これまでに百重にもみずからの力を試み、道に迷った。そうだ、人間は一つの試みであった。ああ、多くの無知と迷いが、われわれの身において身体と化しているのだ!

 「文句なしに、幸福な生は善であり、不幸な生は悪なのだ、という点に再三私は立ち返ってくる。そして《今》私が、《何故》私はほかでもなく幸福に生きるべきなのか、と自問するならば、この問は自ら同語反復的な問題提起だ、と思われるのである。即ち、幸福な生は、それが唯一の正しい生《である》ことを、自ら正当化する、と思われるのである。
「文句なしに、幸福な生は善であり、不幸な生は悪なのだ、という点に再三私は立ち返ってくる。そして《今》私が、《何故》私はほかでもなく幸福に生きるべきなのか、と自問するならば、この問は自ら同語反復的な問題提起だ、と思われるのである。即ち、幸福な生は、それが唯一の正しい生《である》ことを、自ら正当化する、と思われるのである。
 「1. 思考の本質を形づくる結合は、表象の連合とは本来異なる。
「1. 思考の本質を形づくる結合は、表象の連合とは本来異なる。