責務の第1次的ルール
【世界と人間に関する最も自明な真理のみから要請される責務の第1次的ルールが存在し、このルールを受け入れる多数派の態度と、逸脱への社会的圧力だけで維持される、肉体的強さが同じ程度の人々から構成される社会が存在し得る。(ハーバート・ハート(1907-1992))】(1)世界についての最も自明な真理
(2)人間の性質に関する最も自明な真理
(2.1)人間が互いに接近して共存する場合に犯しやすい誤り
(a)暴力の勝手な行使
(b)盗み
(c)欺罔
(3)集団がとる一般的態度だけが、唯一の社会的統制の手段となっているような社会の特徴
(3.1)責務の第1次的ルールは、人間が犯しやすい誤りを抑制する何らかのルールを含む。
(a)暴力の勝手な行使の制限
(b)盗みの制限
(c)欺罔の制限
(3.2)ルールを受け入れ内的視点から見られたルールによって生活する人々と、社会的圧力の恐れによって従う以外はルールを拒否する人々との間に緊張が見出される。
(3.3)非常に緩やかに組織されている社会が存続し得るには、次の条件が必要である。
(3.3.1)社会が、おおよそ同じような肉体的強さをもつ人々から構成されていること。
(3.3.2)ルールを受け入れる人々が多数であり、ルールを拒否する人々が恐れる程度の社会的圧力を維持できること。
「立法機関、裁判所、公機関をまったくもたない社会を想定することはもちろん可能である。
事実、原初的社会に関する多くの研究は、このことがありえたと主張するだけでなく、これまでに責務のルールとして特徴づけてきたようなそれ自身の基準的行動様式に対して集団がとる一般的態度だけが、唯一の社会的統制の手段となっているような社会生活を詳細に描写している。
この種の社会構造はしばしば「慣習」からなるものだと言われている。しかし、この用語は使わないことにしよう。なぜならば、それは、慣習のルールはたいへん古く、他のルールほど社会的圧力によって支えられていないという含みをしばしばもつからである。
これらの含みを避けるために、このような社会構造を責務の第1次的ルール primary rules of obligation からなるものと呼ぼう。社会がそのような第1次的ルールのみで存続していこうとする以上、人間の性質やわれわれの住んでいる世界についていくらかのもっとも自明な真理を認めたならば、必ず満たさなければならない一定の条件がある。
これらの条件の第一として、人間が互いにたいへん接近して共存する場合、犯しやすいが一般に抑制しなければならない、暴力の勝手な行使、盗み、欺罔を何らかの形で制限するルールが存在しなければならない。
われわれが知っている原初的社会では、共同生活に奉仕し貢献するといういろいろな積極的義務を個人に課しているさまざまな他のルールとともに、そのようなルールは事実いつも見られるものである。
第二に、そのような社会にも、既述したようにルールを受けいれる人々と社会的圧力の恐れによって従う以外はルールを拒否する人々との間に緊張が見出されるであろう。
しかし、もし社会がおおよそ同じような肉体的強さをもつ人々からなっていて、しかも非常にゆるやかに組織されていても、それが存続しうるには、後者は少数でしかありえないことは明らかである。というのは、そうでなければルールを拒否する人々は恐れるほどの社会的圧力を感じないだろうからである。
このこともまた、われわれの原初的社会に関する知識によって確証されるのであって、そこでは意見の一致しない人や悪人がいるが、多数は内的視点から見られたルールによって生活しているのである。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法の概念』,第5章 第1次的ルールと第2次的ルールの結合としての法,第3節 法の諸要素,pp.100-101,みすず書房(1976),矢崎光圀(監訳),石井幸三(訳))
(索引:)
 |
(出典:wikipedia)
 「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。では要約に移りましょう。法学や哲学の将来に対する私の展望では、まだ終わっていない仕事がたくさんあります。私の国とあなたがたの国の両方で社会政策の実質的諸問題が個人の諸権利の観点から大いに議論されている時点で、われわれは、基本的人権およびそれらの人権と法を通して追求される他の諸価値との関係についての満足のゆく理論を依然として必要としているのです。したがってまた、もしも法理学において実証主義が最終的に葬られるべきであるとするならば、われわれは、すべての法体系にとって、ハード・ケースの解決の予備としての独自の正当化的諸原理群を含む、拡大された法の概念が、裁判官の任務の記述や遂行を曖昧にせず、それに照明を投ずるであろうということの論証を依然として必要としているのです。しかし現在進んでいる研究から判断すれば、われわれがこれらのものの少なくともあるものを手にするであろう見込みは十分あります。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第2部 アメリカ法理学,5 1776-1976年 哲学の透視図からみた法,pp.178-179,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),深田三徳(訳))
(索引:)
ハーバート・ハート(1907-1992)
ハーバート・ハートの関連書籍(amazon)
検索(ハーバート・ハート)
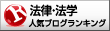
法律・法学ランキング

政治思想ランキング

 「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。
「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。
 「一般に、ものごとを精確に見出されるがままにしておくべき理由は、たしかに何もない。われわれは、ものごとの置かれた状況を少し整理したり、地図をあちこち修正したり、境界や区分をなかり別様に引いたりしたくなるかもしれない。しかしそれでも、次の諸点を常に肝に銘じておくことが賢明である。(a)われわれの日常のことばの厖大な、そしてほとんどの場合、比較的太古からの蓄積のうちに具現された区別は、少なくないし、常に非常に明瞭なわけでもなく、また、そのほとんどは決して単に恣意的なものではないこと、(b)とにかく、われわれ自身の考えに基づいて修正の手を加えることに熱中する前に、われわれが扱わねばならないことは何であるのかを突きとめておくことが必要である、ということ、そして(c)考察領域の何でもない片隅と思われるところで、ことばに修正の手を加えることは、常に隣接分野に予期せぬ影響を及ぼしがちであるということ、である。実際、修正の手を加えることは、しばしば考えられているほど容易なことではないし、しばしば考えられているほど多くの場合に根拠のあることでも、必要なことでもないのであって、それが必要だと考えられるのは、多くの場合、単に、既にわれわれに与えられていることが、曲解されているからにすぎない。そして、ことばの日常的用法の(すべてではないとしても)いくつかを「重要でない」として簡単に片付ける哲学的習慣に、われわれは常にとりわけ気を付けていなければならない。この習慣は、事実の歪曲を実際上避け難いものにしてしまう。」
「一般に、ものごとを精確に見出されるがままにしておくべき理由は、たしかに何もない。われわれは、ものごとの置かれた状況を少し整理したり、地図をあちこち修正したり、境界や区分をなかり別様に引いたりしたくなるかもしれない。しかしそれでも、次の諸点を常に肝に銘じておくことが賢明である。(a)われわれの日常のことばの厖大な、そしてほとんどの場合、比較的太古からの蓄積のうちに具現された区別は、少なくないし、常に非常に明瞭なわけでもなく、また、そのほとんどは決して単に恣意的なものではないこと、(b)とにかく、われわれ自身の考えに基づいて修正の手を加えることに熱中する前に、われわれが扱わねばならないことは何であるのかを突きとめておくことが必要である、ということ、そして(c)考察領域の何でもない片隅と思われるところで、ことばに修正の手を加えることは、常に隣接分野に予期せぬ影響を及ぼしがちであるということ、である。実際、修正の手を加えることは、しばしば考えられているほど容易なことではないし、しばしば考えられているほど多くの場合に根拠のあることでも、必要なことでもないのであって、それが必要だと考えられるのは、多くの場合、単に、既にわれわれに与えられていることが、曲解されているからにすぎない。そして、ことばの日常的用法の(すべてではないとしても)いくつかを「重要でない」として簡単に片付ける哲学的習慣に、われわれは常にとりわけ気を付けていなければならない。この習慣は、事実の歪曲を実際上避け難いものにしてしまう。」

 「あなたが宇宙を任されていて、知性と感覚を備えたあらたな種を創造しようと決意したとする。この種はこれから、地球のように資源が乏しい世界で暮らす。そこは、資源を「持てる者」に分配するのではなく「持たざる者」へ分配することによって、より多くの苦しみが取り除かれ、より多くの幸福が生み出される世界だ。あなたはあらたな生物の心の設計にとりかかる。そして、その生物が互いをどう扱うかを選択する。あなたはあらたな種の選択肢を次の三つに絞った。
「あなたが宇宙を任されていて、知性と感覚を備えたあらたな種を創造しようと決意したとする。この種はこれから、地球のように資源が乏しい世界で暮らす。そこは、資源を「持てる者」に分配するのではなく「持たざる者」へ分配することによって、より多くの苦しみが取り除かれ、より多くの幸福が生み出される世界だ。あなたはあらたな生物の心の設計にとりかかる。そして、その生物が互いをどう扱うかを選択する。あなたはあらたな種の選択肢を次の三つに絞った。



